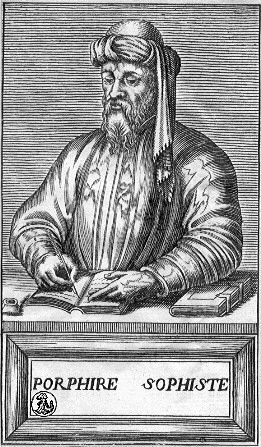■ I-2-(19) 徳について (0.5Mb)
プロティノスは言う。「魂は知性界にも属するものであるが、容易に感性界に堕ちるものである。そこで魂を知性界に留まっている状態にするのが『浄化』であって、『浄化』を経ると魂は知性界に属するヌースと交わって知性界に留まることができるのである。この結果、魂が知性界へと方向を取ることが『徳』である。ただし魂は本来、テアー(観る働き)として『徳』を持っているのであり、われわれは光を受けることによって自分の中に『観る働きとしての徳』があることに気付かなければならない。つまり知性のなかにあるのは徳ではなく、魂のなかにあるのが徳なのである」と。なるほど!
(2014.3.21)
■ I-3-(20) ディアレクティケーについて (0.3Mb)
一般には問答法と呼ばれる ディアレクティケーについて、プロティノスは言う。「それは、それぞれのものについて、「そのそれぞれのものが何であり、いかなる点で他と異なっているのか、そして共通点は何であるのか」をことばでもってあらわすことのできるヘクタス(たくみ)である」、そして「つまり哲学は、ティアレクティケーの援助を得て自然についても考察するのであって、それは他の諸技術が数学を助力者として用いるのに似ているのである」と。
(2014.3.22)
■ I-4-(46)幸福について (0.8Mb)
この作品はプロティノスの生涯の終わり近く267~268に書かれたものである。つまりすでに癩に冒されている時であるともされる。その事実を知った上で彼の幸福についての議論を読むと、彼の壮絶な、知に対する信念と自分自身への覚悟が伝わってくる。「だが。君たちの主張が、幸福は苦しみを受けないこととか病気にならないこととか、不運でないこととか、大きな災害にめぐりあわないこととかのなかにあるということであれば、人はだれでもそのような逆境にあえば、それでもう幸福ではありえないことになっただろう」というアリストテレス派の問いかけに対して、プロティノスは言う。「魂の真の欲求は自分よりすぐれたものに向けられており、それが魂のなかにあらわれると、魂はそれに満たされ静かになるのであって、実にこれこそ、魂の求めている真の生き方なのである」という宣言の説得力はそれゆえに看過できない。
さらにプロティノスは、この章の終わりに、「彼自身(知性)はそれ(肉体)とは別のものであるから、それを 捨てても別に差し支え はないし、自然によって定められた適当な時期(死期)がくると、それを捨て去るだろう」、「それに、彼自身がその時期について決定する権利をもってもいるのである」と、自死を賢者の権利とする。勿論、これは主を信じる者にはあり得ない言葉である。そして、死を目前にした自分自身の肉体をリュラ(琴)に例えて、「だが、その琴が使用に堪えなくなると、彼はほかの琴に取り換えるか、 あるいは琴の使用をやめ、琴に向けられていた活動を放棄してしまうだろう」と述べる。だが、プロティノスは簡単に自死を選ぶのではなく、自身の肉体を軽蔑するのでもない。この章の最後の言葉である、「しかし、はじめにその楽器が彼に与えられたことは、決して意味のないことではなかった。彼は今まで何度もその楽器を用いたことがあるからである」にその考えを込めているのであり、彼の病状を考えるとその覚悟に感銘を受けるのである。
(2014.3.28)
■ I-5-(36)幸福は時間によって増大するか (0.2Mb)
ここでプロティノスは、永遠の時間と瞬間的な時間を対峙させつつ過去と現在、そして未来の時間軸における幸福の位置づけについて論ずる。この論は幸福については「幸福について」と併せ読むべきだし、時間については別項と併せて読むことによってその意義がより明確になるであろう、と思われる。
(2014.3.29)
■ I-6-(1)美について (0.6Mb)
プロティノスは美を感性界における美と知性界における美を分けた上で、感性界における美は、感性界の存在であるヒュレー(質料あるいは素材)にエイドス(形)がやってくることによって美が現れると云う。そしてその美の認識は、感覚という力が、物体に宿るエイドスを見て、それと協和する魂の内にあるエイドスとへと橋渡しすることで人のなかで実現される、と云う。プロティノスのこの章における眼目は、知性界にある至高存在である善に至る前段階を示すために、まず善の一部である美を見ることを最初の到達点に設定して、その方法を示すことにある。
プロティノスによれば、そのために必要なのが魂の眼すなわち心眼であり、「めざめたばかりの心眼は、光り輝いているものをすこしも見ることはできない」ので、まずこの世の彫像制作者のようになって、自分自身が「君がこのようにして純一なものとなるのを妨げるものを何ひとつとしてもたず、また、君自身に付着しているような別の混じりものは君の内には何ひとつとしてなく、君自身のすべてがただまことの光のみとなって…自身の内につくりあげた彫像となっている君自身を見る時、その時こそ、君は心眼そのものとなって自信に満ちあふれていることだろう」と云うのである。
プロティノスはこのように、至高の善である一者にわれわれは似た者となり得るという信念の下に、議論を展開するのである。当然のように推論されるのであるが、これがキリスト教の神を念頭に置いた上の議論であることを否定することは難しいと思われる。
(2014.3.31)
■ I-7-(54)第一の善とその他の善について (0.1Mb)
まず、最善なるものは静止しているとプロティノスは言う。なぜなら、善が、最善なるものへの欲求と活動であるならば、最善なるものはその究極の状態であるからである。さらに彼は言う。
魂は知性を通してこの最善へ向かっているのであるが、魂のないものでさえ、その存在は最善からの形相が与えられた結果であるので、善にあずかっているといえる。すなわち、生命と知性の両方をもつものは、二つの最善への道を持っていることになる。
だが最善への道が示されているとはいえ、生には劣悪なものが混じり合っているのであり悪しきことから離れられない。であるから、魂が肉体を切り捨ててこの劣悪なものから逃れるのは善きことであると。
(2014.4.4)
■ I-8-(51)悪とはなにか、そしてどこから生じるのか (0.8Mb)
プロティノスはヒュレー(素材)を感性界にあるゆえに悪しきものとするのであるが、この章ではこれをさらに進めて、ヒュレーを悪であると主張する。もっとも、この訳はドイツ語訳をさらに日本語にしたものであるので、「悪しきもの」と「悪」が完全に分離されていない可能性がある。ただし、プロティノスは「善」が知性界に存在する最高の一者であるとしているので、これと「悪」を対峙させているわけではない。あくまでも、プロティノスとしては「悪しきもの」は善すなわち知性の欠如である。
また、アリストテレスが「在るもの」がヒュレー(素材もしくは質料)にエイドス(形相)が内在しているとしたのに対し、プロティノスはプラトンに倣い「ヒュレーにエイドスがやってくる」という表現を用いて両者の関係を表す。問題は「悪しきもの」が単に魂の上昇を妨げるものでしかないのに、「悪」が例えば「悪霊」というような概念によってキリスト教において現れたので、これを説明しなければならない事態にギリシア哲学が陥ったことにある。
そこで、プロティノスは「在るもの」にエイドスがやって来ていない状態が「悪」であると定義したようだ。ただし、「在るもの」はロゴスであるキリストによって世界の始まりにおいて「在るもの」になったので、ヒュレーそのものが現在も存在するのか、という問題が起きた。そこで「存在しない」という「あるもの」が「悪であるヒュレー」であるとして問題を回避したように見える。ただし、ヒュレーにエイドスが与えられて「生成」が起きるという話があるので、「生成」が今もあるのかという疑問があって、これらの関係についてはさらに読み進めなければわからないようだ。
()
■ I-9-(16)自殺について (0.01Mb)
もちろん、この論において、プロティノスはソクラテスを念頭においている事は間違いないであろう。
肉体の調和が存在しなくなったとき、肉体は魂をとどめる力を失って、魂は肉体を離れるのであるが、肉体が魂を見捨てない前にあえて肉体を死滅させると、「魂は情念からは自由になれず、不愉快さや苦しみや怒りがつきまとう」ことになるとする。
従って、自ら肉体を死滅させるべきでないが、賢者であれば、「無条件に選択されるべきことではないけれども、状況によっては選択されるべきことのひとつ」と看做すこともある得るとするのである。しかも、魂の向上の可能性のある限り、魂を肉体から連れ出してはならないとも言う。
(2016.1.28)
■ II-1-(40)天について (0.6Mb)
プロティノスは宇宙そして天体も生きるものであり、それゆえに、魂と身体を持つ事を主張する。しかし、地上の生きものは生まれ変わる種としては永遠であるかもしれないが、その個は滅ぶ。それでは、天体は個体であるのに、どうして永久性を持つのかというのが、この論の主題である。
単に天体の永久性があるように見えても、それが単に地上のものに比べて長い間存在するのであれば、地上のものと本性的には違いはないだろうとした上で、次に、天体が個体としての永久性を持つならば、身体に地上のものとの間に違いがある筈で、それは何かという問題にプロティノスは移行する。
身体に永久性をもたらすためには、身体からの流出がなくまた身体を養う必要のないことが必要である。星々は火であるのに、それが流出しないのは、本来、火は昇るものではあっても降下することはなく、上方に止まっているためにであり、地上の炎は沸騰であるが、天の火は静かで落ち着いているのである。さらに宇宙は、直知界に隣接する、力あるものだから、そこから何かが逃れることはないのである。また、星々が火だけでできているとも言い難い、星々が固さを持つなら、土をも持つ筈である。しかし、土を天に上げることは自然の定めに反しているから、天体は単独の火や土ではなくその結合体が作り出しているのであり、プラトンもこれを言っている、とする。
また、天体は静止しているか回転しているかである。この場合の回転も、本性的に回転しているのであって、それゆえに何かにより養われなくとも永遠である。以上がプロティノスのいう天体の本性である。
ここで、筆者の立つ処を示しておかなければならないであろう。なぜかと言えば、現代科学によれば、もちろん天体は火でもないし、魂と身体を持つとも言い難い。だが、その事実に依って、プロティノスの論は野蛮で無意味であると看做すべきであろうか。いや、そうではあるまい。プロティノスは、もちろん、器械による人間の感覚の拡大という人間の歴史の転換点の以前の人であり、人間の感覚だけを頼りに、矛盾のない論理を打ち立てて、その矛盾のなさを議論の正しさの論拠として、思考の展開を行った哲学者である。彼は、「哲学という、魂にそなわる知への希求」に導かれて、思考し、知を求める人であって、私は、彼の思考の展開の内に見られる、「人間の知への希求」の尊さを感じるゆえに、プロティノスの議論の展開を受け入れるのである。
ここで言う、矛盾のないことを議論の正しさとする、とは、例えば物の落下速度が、物の重さに依らないことを示す議論である。それは、例えば次のような議論の展開である。重さ1ドラクマの物体と2ドラクマの物体の落下速度を比べて、1ドラクマの物体の落下速度の方が遅いと主張するのであれば、1ドラクマの物体を二つ入れた袋は2ドラクマの物体より遅い筈であるが、これを、2ドラクマの物体を入れた袋と比較すれば、どちらも2ドラクマの重さを持つ袋であって、落下速度は等しくなるであろう。従って、落下速度は物の重さによらないのである。
(2016.3.1)
■ II-2-(14)天の動きについて (0.3Mb)
プロティノスは天の火つまり星々が何故動くのかを問う。まず天に昇った魂は英知に近づいている筈なので、満ち足りて静止している筈であると問いを立てる。一方、魂も天も生命あるものであるから、その本質ゆえに動くものであるべきだ、とする。一方、天の星々が火の本性を持つならば、火は直進するものの筈でもある。しかし天の火は行き着くところまで、つまり天という最終的な位置にまで昇りつめたのであるから、直進して去ってしまうのでもなく、運動を保持しているのだとすると、中心のまわりを回ることによって、運動しつつ静止している中心に傾いているのである。しかも魂はあらゆるところに遍在しているべきであるから、円を描いて回ることで、あらゆる場所を訪問することができる。
一方、たとえば人間の肉体のような物体はどうであろうか。魂と物質の間に類比が成り立つべきであるとすると、物質も何かのまわりを回るのであろうが、物質の場合はこちら側が中心なのである。つまり、プロティノスはここで、人間の目に見える天の火という物体は、地球を中心に回っているとするのである。
では、もとに戻って、魂がめぐるその中心は何であろうか。これについてプロティノスは言うのである。「神がすべてのものの内にいますならば、神とともにありたいと望む魂は、神のまわりで動くほかはない」と。
このようなわけで、下の力すなわち我々や動物は、天につながる上の力によってぐるりと取り囲まれていて、それゆえに上の力の方へ傾き、そして向き直るのである。そして、英知はそれ自身のまわりを動いているのだから、静止しつつかつ動いているのである。だから「同じようにこの世界もまた、円く(動くこと)によって、動くと同時に静止している」とプロティノスは述べる。
つまり、地動説である。
(2016.4.21)
■ II-3-(52)星は引き起こすかどうかについて (0.9Mb)
()
■ II-4-(12)ヒュレー(素材)について (0.7Mb)
プロティノスはヒュレーについて更に論を進める。ヒュレーは悪であるという前提のもとに、話はすすむのであるが、さらにプロティノスはヒュレーとエイドスが結合して、可能態から現実態に変わる過程について、この章に引き続く章で述べるので、首尾一貫した理解を得るために、これらを総合的に読み込む必要がある。
プロティノスは知性界の有を超えた一者を設定したため、知性界の有には始原があるとせねばならなかった。そのため、感性界に対する優位性を保持するために、始原はあるが、その素材は永久に他者に依存している点では不生のもの、とした。なおかつ知性界の有に素材の必要性を認めたため、その素材はロゴス(条理)の中に存在するとして、感性界の素材とは違うことを強調するのである。こうして、知性界の優越性を示すためのあらゆる悪が、感性界に背負わされた訳である。
ところで、有るものには性質があるとされるのだが、この性質とは何か、ヒュレーにエイドスが与えられた時、性質はどのようにして有るものと関係するのか、という面倒な話があって、まず性質という日本語の単語は何に対する訳であるのかを明らかにする必要がある。
(2014.4.19)
■ II-5-(25)可能的なものと現実的なものについて (0.4Mb)
この章をマッピングするにあたって、訳者の用いる用語を自分なりに書換えた。なぜかというと、訳者が用いている「可能的(τὸ δυνάμει εἶναι)」という言葉は日本語として一般的には用いられないのだが、これと対置される「現実的(τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι)」という言葉が、日本語として一般的に用いられ、かつこの言葉が「実現に至らないケースの割合が低いという推測を、ある対象に与える」というニュアンスを持っているため、何よりもまず自分自身の理解にバイアスがかかるためである。
ここでは、
現実性、現実態、をエネルゲイアに
現実的、を現実態にある、に
と
可能性、可能態、をデュナミスに
可能的、を可能態にある、に
に加えて
現実態にある状態を現実的と訳された以外の、現実的(リアリスティックな)をそのまま現実的、に、という置き換えをおこなった。
さて(上記のように置き換えた上で)、プロティノスは、知性界と感性界の両方について、「現実態にあるもの」を「有であるもの(感性界においては感性が有であると感じるもの)」とし、現実態にあるものは「素材をもたないもの(英知など)」と「素材から現実態となったもの(現実態にあり可能態も持ちうるものが含まれる)」に分け、これ以外を「素材」であるとする。素材は有ではない何かなので、「素材は単に可能的にのみ有る」(訳による)とプロティノスは言う。単語を微妙に使い分ける必要があるので、プロティノスも、「このものの実相は非有に存するのだから、現実態として何らかの有であることは、このものにとってほど遠いことである」とか、「このものは真実に有ることから逸脱しているので、有らぬことにおいて有ることをもたねばならない」などと持って回った言い方をしている。
プロティノスはデュミナス(可能態)という言葉を使って、つまり、素材をその形相を得て現実態にある有るものに転換するという、プロセスにより説明しようとしたため、「もし素材を不滅のものとして保存しなければならぬとすれば、それを素材として保存しなければならない」という素材の不滅性が導き出されたり、「素材は可能的に何かであるものではなくて、可能的にすべてである」や「現実態として何らかの有であることは、このものにとってほど遠いことである」という、この世の最大の可能性そのものが素材であるという結論が導き出されたりする。
その結果、不滅にして最大の可能性がヒュレーであるというのは、プロティノスが「ただ一つそれに残されている道は、単に可能的にのみあり、弱々しい、おぼろな、どのようにも形を与えられえない幻影であることである」と強調しても、ヒュレーが「悪」であるとされる故に、その強力さが逆に目立つのである。
(2014.4.13)
■ II-6-(17)実体について、あるいは性質について (0.3Mb)
始めに、性質についてプロティノスが何を言いたいのかを明らかにするために、まず、性質は何かを知る必要がある。さて、調べると、プロティノスがποιότητεςと記した概念を英語では、qualityあるいはpropertyと訳するのであるが、フランス語では、qualitéであるので、英語はこれが元になっているものと思われる。だが、qualitéはポジティブな性質を表す場合に使われることが多いので、この用語がプロティノスの意図したものと合致するかという点については疑問が残る。とは云え、ではギリシア語で議論するか、ともならないので、「性質」という単語を使って話を整理していこうと思う。
さて、性質について、プロティノスはそれを、ウーシアの上に形づけられている、何らかの性状であり、それらは(直知界においては)働きである。「たとえば、徳と悪徳、醜さと美しさ、健康、あるふうに形づけられていることが性質である…だから、結局、性質とは、すでに存在するウーシアの上に加わる何らかの性状である」として、結論としては(直知界において)、「他者の形相とならないで、いつでもたまたま付随するだけのもの、これが、しかもこれのみが、純然たる性質である」とするのであるが、この結論は逆に言えば、他者に入り込む何らかの性質があるのだということを、後でプロティノスが言おうとしたための布石なのだろうか、などと思ってみて、性質についての完全な理解は先送りにしてあるところだ。
一方、「性質(ποιότητες)の説明について、ストア派において、世界のうちに存在するとは、性質づけられた物質的なものとして個別的に存在することに他ならない。したがって,個物は、「個別的な性質」(ἰδίως ποιόν) によって性質づけられており、それら諸個物の間で共有される性質が「共通の性質」(κοινῶς ποιόν)ということになる」、バシレイオスのウーシア - ヒュポスタシス論、土橋茂樹、中世思想研究 (51), 25-41, 2009 、という記述も見つけて、プロティノスはストア派の言う性質に対して、何らかの意見あるいは反駁を言おうと思っていたのだが、十分に整理されていないうちに、ポルフィリオスによりまとめられることになった、という話もあるのではないかと思ったりもしている
(2014.4.19)
■ II-7-(37)通全融合について (0.2Mb)
()
■ II-8-(35)視覚について、または遠くのものが小さく見えるのはなぜか
()
■ II-9-(33)グノーシス派に対して (1.0Mb)
プロティノスの記述において着目すべきは、プロティノスの生きている時代の、グノーシス、いわば生のグノーシスに対して、プロティノスはその考えを批判しているのであるが、それは逆に言えば、まだキリスト教が完全には支配的思想となっていない時期のグノーシスを、プロティノスが観察した結果が記述されていると考えられる点である。
さて、プロティノスの記述をマッピングしていくと、プロティノスの云うグノーシスが余りにインド哲学、誤解を恐れずに言えばヴェーダーンタ学派に近いことに驚く。例えば、プロティノスの言う「(世界の)原型は彼らによれば、その制作者がすでにこの世界へ傾いたときの産物なのである」の、「傾いた」あるいは「迷った」という語を伴う不可思議なグノーシスの論の説明は、ヴェーダーンタ学派の説と関連しているのではと思い至る。ヴェーダーンタ学派の説にある、最高神が世界を創造するのは、その迷いのためであって、「アートマンなる神は、みずからの幻力(迷妄、マーヤー)によって、みずから自己を分別する」と一致するように思われるのだ(中村元, 1968, p1-45)。しかし、プロティノス(205 - 270)の活躍した期間を考えると、この考えがヴェーダーンタ哲学をとりまとめたシャンカラ(700~750)以前に成立していたことを探し出さねばならない。
で、さらに調査を進めると、プロティノスがグノーシスについて言う、「傾いた」という語が、サーンキヤ学派の説により近いのではないかという疑問も生まれた。古典サーンキヤ学派の云う、「永遠に変化することのないプルシャの観照を契機に、物質原因あるいは第一原因といわるプラクリティの平衡が破れると、これから様々な原理が展開してゆく」が、これを説明しているのではないかと気が付いた。そこで、またも頼みの中村元先生(中村元, 1996)、サーンキヤ学派の論をマッピングしていくと、まさにプロティノスの言と一致しているのが見つかった。見つかっただけでなく、サーンキヤ学派とグノーシスのピタゴラス派の関連が見られたり、さらにアナクサゴラス(BC500-428)との関係が推定されたり、つまるところ、インドーギリシアの関係は一方的なものではなく、相互に哲学的な交流のあったことが考えられるのだ。
ということで、両者の関係については別項をたてて検討を進めることにした。
(2014.7.21)
■ III-1-(3)運命について (0.5Mb)
例えば、「グノーシス派に対して」などと比べて、プロティノスのこの章の書きっぷりを見ると、彼が若い時代にこれを記述したように思われる。後年の著述に比べるとよく云えば大胆にして簡明、逆に云えば、慎重さに欠けるように読めて、いかにも若々しさが感じられるのだ。運命については、天体の運行に人間の暮らしが支配されているのだと説き、それゆえに、それぞれのものの有り方を定める、ただ一つとみなされる始原があって、また、これから始まって、すべてのものが種子的原理にしたがって成就される、その故に人間の行動についても「表象は先行する諸原因にしたがっており、また(行為への)発動は表象にしたがっていることになる」という考え方が主張される。こういう清々しいまでの率直さと自分に対する自信は、まだ病に犯されない時分の、プロティノスの論が、また人を惹き付ける所以であると思われる。
ところで、ただこれだけでは、人間の意志決定の存在する余地がないので、本来は彼の言うように、「自由であり、宇宙的因果の外にある」個々の魂が、「自らは変えられることなく、むしろそれらの境遇を変えようとするので、その結果、ある状況を変化せしめる」とあるように、意志を表すのである。ただし、「いったん肉体の内に入りこむと、他の事物と一緒に(因果系列の中に)配置されるので、もはやあらゆることに関して権力をもつわけにはいかなくなる」ということとなって、「運命とは外部からの原因であると考える人々にとって」は、「行為は運命にしたがって行うのだと言って、おそらく正しいだろう」、ということになるのである。
プロティノスのこの論に至るギリシア哲学者の考え方に、異論を唱えるのはなかなか難しいことだ。特に全てが因果の系列の上にある、という考え方に対する異議は、不確実性(Uncertainty)の導入において提出されるのであるが、不確実性の存在の提案は、数学の実在を確信する数学者が確率論を論ずるまでは、社会的な受け入れには困難を伴うであろうことが予想される。例えば、骰子の出目についての議論が賭博という文脈の下でしか行われなければ、その考察が社会的信頼を得ることはできないであろう。数学が世界の一部分ではなく、数学自体が実在する世界であるという確信が始めにあって、その下で骰子の出目を抽象化した議論が行われなければ、確率論は認められなかったであろう。ギリシア・ローマ文化は偉大であるが、確率論が出現しなかったのは、条件が整わなかった故とは云え、残念なことではある。(2014/5/24)
(2014.5.22)
■ III-2-(47)神のはからいについて第一編・III-3-(48)第二編 (1.5Mb)
まず最初に日本語のタイトルについてであるが、ギリシア語エネアデスの当該する章のタイトルは「Περὶ προνοίας」であって、「プロノイアについて」とでも訳すのが適切であろうと思われる。訳者はこれに「神の」という前置詞を付け、その解説として「『神のプロノイア』というような表現は早い時期から現れている。たとえば、エウリピデス『フェニキアの女たち,637』、プラトン『ティマイオス,30c,44c』などにある」などとしているが、エネアデスを読み解く場合に、背景としてのキリスト教の存在を無視することはできないのは明らかなので、このタイトルは、プロティノスが何を指して「神」と呼んでいるのだろうか、という話に直ちにつながって、読者をして緊張させるのである。
実際に当該する章の本文においては、「神」という単語とともに「神々」という単語が使われていて、キリスト教の言う「神」との違いを、複数形によって表すという、慎重な取り扱いを行っているのに、訳者のこのタイトルの付け方は、プロティノスの苦心を無視した「神の」安易な取り扱いであると言わざるを得ない。
プロノイアが「プロ(あらかじめ)」と「ノイア(配慮すること)」を語源として、原理が世界の在り方を支配するということを意味すること、そしてキリスト教における、「オイコス(家」と「ノモス(秩序)」から成るオイコノミアοἰκονομίαが、摂理的配慮あるいは救いの営みという意味をもつこと(例えば、一〇〇の実践的・神学的主要則、新神学者シメオン、13)を考えると、両者の概念には重なり合う部分があると推定されるのであり、それゆえに、プロノイアに「神の」という言葉を接続することに違和感を感じるのである。
以上はローカルな話であった。さて、この世は何故平等ではなくて、善い者と悪い者、あるいは優れた者と劣った者があるのかとプロティノスは問いかける。そしてプロティノス自身の答えは、「原理が自己を単に異なるものたらしめるばあいにではなくて、そのうえまた敵対的なものたらしめるばあいにこそ、原理は完全なものであるだろう」というものであり、自らを英知のために闘う者とするプロティノスらしいと言う他ない。
プロティノスがこれ程にあからさまに言うのは、プロティノスの、人間が最良でも最悪でもないという位置にある、というローマの考えに立っているからであり、またこれこそが、プロティノスをキリスト教から独立した思想者にしているところであると思われる。だが、確定された正義を根底に置くキリスト教とは距離をおいて、真理を追求するプラトン主義者と自らを定義するゆえに、つまり人間を相対的に考えるその相対性のために、その論は揺れ動くのであり、その論を確固たるものにするためにプロティノスは苦闘するのである。
プロティノスは、出来事とはその原因を追求することのできる観察対象であって、現世の全ては直知界に存在する魂の反映であり、さらにその直知界はヌース(英知)により支配・構成されている、という上方から下方に向かって流れる何ものかがそれを規定する、階層的な世界を提示するのである。そして階層的世界には階層を分ける境界があるゆえに、下方からその境界面を通して上方を完全に見通すことはできない、のであり、それゆえにわれわれ人間が何らかの手段、例えば徳によってこの境界面を通り抜け、英知に達することを目的とし、その道筋を明らかにすることこそ、プラトンを尊敬する者の務めであると考えるのである。だが、下方からは上方を完全には見通すことのできないという、いわば不完全な状況は、人間を相対的に考えるという原則から導き出されたものでもあるゆえに、避けることができないのである。
こうして、人間を相対的な位置に置きつつ、絶対的なキリスト教教義に対抗するために、プロティノスはこの階層的世界の記述を複雑化させ、同時にその記述を矛盾のないものとするために、論考を重ねることになる。
始めに、この世に、善い者と悪い者、あるいは優れた者と劣った者が存在するのは、基本的には階層的世界の原理から導き出される当然の結果であるとプロティノスは言う。この世は直知界の魂に照らされた演劇のようなものであり、そこでわれわれは役者として原理が作った台本のとおりに演ずるのであると、その状況を説明した上で、ヒュレー(素材)に作用する原理そのものが、全てのものが等しくあるべきではないという選択をした故に、この世界は優れた者と劣った者があるのだと言うのである。
またプロティノスは、善い者と悪い者、あるいは優れた者と劣った者の関係が永続するのではないとして、いわば因果応報が、このプロノイア(はからい)により起こるとする。これを説明して、「現世で悪人となって死ぬだけでは事はすまないのであって、以前の行いには原理と自然からして、それに相応するだけのことがいつでも伴う(第一編 8)」としたり、「この法は、善い人となった者には善い生が、また悪人にはその反対のものが伴うだろうし、先々でも待ち受けている、と定める(第一編 9)」と述べ、さらには、「原理が変化することによって、以前は人間であった魂が牡牛の魂になる、という意味である(第二編 4)」と次の生が人間でない場合にも言及するのである。
ただし、プロティノスのローマ人らしいところは、悪い者、劣った者を否定するのではなく、「より善いものがないならば、どうしてより悪い何かが存在しえようか。あるいはより悪いものがなくて、どうしてより善いものがありえようか(第二編 7)」とその存在意義を認めるところにある。また、「そもそもこの世界の内にあるより悪いものを除去すべきだと考える人びとは、はからいそのものを除去しようとしているのである(第二編 7)」と述べて、ヌースに起源をもつ原理の、人間に対する優越性を述べるのである。
また、プロティノスは悪い者、劣った者にも存在価値があるとすると同時に、そしてそれにも関わらず、世界の下方部分は申し分のない状態にあって、秩序にあずかっているとみなす。プロティノスはこの仕組みを「神力が徳を強めるために用いる多様な手立てによって、常に上方へと引き上げられているので、人類は理性的であることを失わないで、最高度にではないにしても知恵と英知と学術技芸と正義にあずかっている(第一編 9)」と述べる。
プロノイア論がキリスト教にどのように影響を与えていったかについては、調査が足りないのであるが、その考え方が、一方では神の恩寵、一方では予定説へと結びついていくことは容易に推定できるのである。
(2014/6/4)
■ III-4-(15)われわれを割り当てられた守護霊について (0.4Mb)
訳者がこの章につけたタイトル「われわれを割り当てられた守護霊について」は、誤解を招く表現ではないだろうか。おそらく訳者は英語訳のタイトルである"Our Tutelary Spirit"から「守護霊」という単語を、δʹ Περὶ τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς δαίμονοςのタイトルにおけるダイモーンの日本語訳として用いたものと思われるが、プロティノスの論を読んだ後からは適切とは思われないのである。むしろ、「われわれに割り当てられたダイモーンについて」位で良かったのではないか。
なぜかと言えば、この論でプロティノスは、ダイモーンそのものについて論ずるのではなく、例えば、人間の魂が肉体を離脱した後に、次の生を選ぶ時に何が起こるかについて論ずる時に、初めて次の生とダイモーンの関係について言及するなど、ダイモーンに対して常に慎重な態度を保って議論をすすめる。すなわち、プラトンやギリシャの哲学者がダイモーンという概念について述べていることに反論するのではなく、その概念をプロティノス自身の考え方に沿って再解釈しているのである。
その再解釈とは、「もし人が自分の上に位置を占める守護霊にしたがうことができれば、彼はその守護霊の生をおくることによって、そして彼を導く<彼自身の優れた部分>に主導権を与えることによって、上位の世界に位置を占めることになる」や、また「守護霊については、『人の選んだ運命を成就させるもの』と(プラトンの著述に)述べられているが」、あるいは「それゆえ、『われわれが(守護霊を)選ぶことになるであろう(プラトンの国家を引用)』と言われているのは、正しいことである」などとして、彼の尊敬するプラトンの言葉を引きつつも、プロティノスの意見、すなわち、人間の生の主導権は人間自身の優れた部分にあり、ダイモーンは導き手である、とするものである。
このように、プロティノスが、プラトンの記述を尊重しつつ、ダイモーンの擬人化あるいは神化を避けて、これが人間のもつ優れた部分に優越することはないとして、論を進めていることを考えれば、ダイモーンを人間との関係の曖昧な日本語の語彙である「守護霊」と呼ぶのは適切でないと言うべきであろう。
むしろ、プロティノスは、ダイモーンを擬人化するのではなく、例えば「徳」のような「もの」として捉えることを目指していると、考えることもできるのではないか。仮に、ダイモーンが人間の生を導く「もの」、いわば、航海におけるコンパスのようなものであるとして、このプロティノスの論を読んでみても、実際に不都合は生じないのである。
さらにプロティノスは人間の最上の例である賢者について、賢者とダイモーンの関係を述べることによって、その他の人間とダイモーンとの関係を暗示するのである。プロティノスは賢者の魂が肉体を離脱したその後について言う。「上位の世界にやってくる魂たちの或るものは感性界に住み、他は感性界の外に住むのである」、そして感性界の最上部にやってきた魂について、「感性界に住む魂のそれぞれは、この世での理性的な活動の多少に応じて、太陽や他の惑星に住んだり、恒星に住んだりするのである」ので、「われわれの魂は、この種の神を-ーそれが星そのものであれ、その力を超えた神であれ-ーまた守護霊として用いることにもなるのである」と述べる。また感性界を超えて、知性界にまで到達した魂であれば、「感性界の外に居を構えた魂たちは、守護霊的なものや一切の誕生の定めを超え、可視的世界にあるものすべてを超えているのである」として、もはやダイモーンとの係わりを超えるとしている。
だが、賢者にもなれず、上位の位置に移行して、新たなより優れた人間の生をおくるために、生の選択の主導権をもつこともできなかった人間が残るのであるが、これらの人間についてプロティノスは、「ふたたびこの世界に向かうばあいに、その魂は、これからおくろうとする生活にしたがって、以前と同じ守護霊か別の守護霊を持つのである」として、このばあいに人間は、自分が運命を選択するのではなく、必然により運命が割り当てられるのだと言うのである。
(2014/6/13)
■ III-5-(50)エロスについて (0.7Mb)
まずプロティノスは、エロスが、人間にある種の情念を催させる者であることを言ってから、その情念がどのようなものであるかを最初に示す。彼が示すように、世間一般の人々が興味津々なのは、エロスを媒介とする自分と他人の関係だからである。そして、「これが或る美しいものと一体になりたいとねがう魂のなかに生じるということを知らない者は、おそらくだれもいない」のだが、これがさらに、「美そのものと親しくしている思慮深き人から生じ(るもの)」と、プロティノスらしい言い表し方といおうか、「或る種の見苦しい行為を成し遂げることによって終わることをねがう欲求」の、二通りに分けられると言うのである。勿論、この後、「或る種の見苦しい行為」についての言及はないのだ。
さて、プロティノスが、「神のようなプラトンの見解」と呼ぶほどに尊敬する、プラトンの、エロスに関する記述について、プロティノスは、「彼は『饗宴』のなかで、エロスはアプロディテから生まれたのではなく、『ペニアを母としポロスを父として、アプロディテの誕生祝いの日に生まれた』と述べている」。プロティノスは、この断定的なエロスに関する記述を、いかに筋道だてて、彼の考えと合致するように再解釈するかに腐心するのである。このためにプロティノスは様々な先例やプラトンの記述を引用するのであるが、結果としては、この論は、単なるエロスについての記述に終わらず、ダイモーンが如何なる位置づけにあるかを明らかにしたり、エロスの誕生のプロセスを、一者からの知の流出とロゴスとの関係、ロゴスと魂の関係の話に転換するという副次的な効果を生むことになって、彼の一者に関わる思考の強化にエロスが援用されることとなるのである。
最初にプロティノスはエロスの擬人化を慎重に否定する。そしてエロスは、高度な魂がヌースから生まれたとき、ヌースを熱烈に恋い焦がれるように見つめる、生まれたばかりの魂の眼であるとする。するとこのような眼はより下位の魂にも備わっている筈で、高度の魂は普遍的なエロスを持ち、下位の魂達は、それぞれ自分にふさわしいエロスをもつのだと言う。したがって、普遍的なエロスは、高度な魂の存在する知性界において、高度な魂に寄り添っているゆえに神であり、この世にある魂にしたがうエロスは、ダイモーンであると。
そこで、感性界にあるエロスを含む、ダイモーンとは何であるかについて、プロティノスは、「ダイモーンは神々に次ぐもので、永生不死ではあるけれども、神々とわれわれ人間族との中間に位置するもので、すでにわれわれの方に傾いている」、つまり情念を持つ、感性界にあるもの、であると言う。しかし、ここで問題が起きる。感性界にあるダイモーンが、何でできあがっているかという問題である。ダイモーンが永生不死である以上、われわれと同じ素材からできている筈はないが、一方、われわれに影響を与えるという点で、混じり合うとも云えるのである。知性界にある清浄なものがわれわれと混じり合う筈がないのに、である。
ここで、プロティノスは、『ペニアを母としポロスを父として、アプロディテの誕生祝いの日に生まれた』というプラトンの言を引用し、再解釈を試みる。そこで、プロティノスは、このポロスとは知性界にあるヌースのなかにある、ヌースに続く存在であるロゴスのことであり、このロゴスがヌースから溢れ出て、拡散し、魂の中に入り込んでいる状態が、アプロディテの誕生の宴の神酒、ネクタルに酔ったポロスであるとする。また、ヌースは自足していてロゴスを取り込むことはないが、その豊かさ故に溢れ出し、それはヌースにあるときよりも劣った状態となるゆえに、感性界とも連絡できるダイモーンとして生まれるのだと言うのである。
ペニアについては、ペニアが困窮を表すゆえに、エロスは満ち足りることがないという性質を持つのであると。
つまり、プロティノスは、ヌースが感性界に降りることはないが、ヌースのなかにあるロゴスはヌースから溢れ出ることによって、より劣った状態ではあるが感性界の魂に入り込むことができると、述べているのである。即ち、ロゴスをキリストと読み替えることによって、ただちに、キリスト・ロゴス論に発展することが予想できるのである。ただし、プロティノスがプラトンを敬愛するあまり、素朴な神々と人間に寄り添うダイモーンを、その論理構造に取り入れざるを得ず、キリスト教とは無関係なデーモンが引き継がれることにもなるのである。
なお、自然に反したエロスは、ダイモーンでは全くなく、魂の悪徳とともに生じた、単なる自己の類似物に過ぎないとも、プロティノスは付け加えるのである。
(2014/6/16)
■ III-6-(26)非物体的なものの非受動性について (1.6Mb)
ここでプロティノスは非物体的なもの、すなわち魂と素材を同時に取り上げ、そのどちらも非受動性を持つこと、プロティノスに従えば、受動して変容するものに非ざること、つまりそれ自身は変化しないものであることを述べる。述べるにあたっては、プラトンの言説に直接的には矛盾しないこと、を第一とし、これに再解釈を施すのである。魂と素材という明らかにし難いものを同時に扱うのであるから、論が微に入り細を穿つことになるのは仕方がない。そこで、プロティノスはまず魂を肯定的に捉えて、これと対比させることにより素材の非受動性について説明するという方法をとる。
なぜ非受動性つまり変化しないことを重要視するかと云えば、変化しないことが永遠の証しだからである。魂と素材という、この感性界を作り上げているものが永遠であるゆえに、感性界も永遠であることが担保されるのである。一番最初に、プロティノスは「魂は、物体が熱せられて熱くなったり、冷やされて冷たくなったりするような、そのような変化や変容を受けることはない」という結論を述べて、この結論を得る為の長々しい議論を開始するのである。また、魂と素材に関する議論は同時に行われるので、その論は錯綜するのである。
最初は魂について述べられるのであるが、まず前提条件として、魂のウーシア(本質)は、形成原理であるところのロゴスであるとする。次にプロティノスは、魂には肉体や感覚に係る「受動的な部分」と「受動的な部分よりも高度な部分」があるとして、その「高度な部分」から、論は展開される。「高度な部分」とは魂の理知的な部分とされるが、この理知的な部分は、さらに部分に分けることができる。なぜ部分が必要かといえば、悪徳の存在が魂の非受動性と矛盾しないことを示す為である。プロティノスは、悪徳とはそれぞれの部分が不調和な状態にあり、悪徳があるとき、ある部分が劣悪になるのだという。非受動なのになぜ劣悪となるのかが、次に示される。
少なくとも魂の高度な部分は、感性界の影響を受けることはないので、劣悪な魂の部分とは、本来理知的であるべき部分が、偽りの「思いなし」をするために悪徳を作り出したのだと。であるから、理知的な部分が調和しているときは、それぞれがウーシアによって働き、そのウーシアゆえにロゴスに耳を傾けているのだと。つまり、悪徳の状態にない時には、「魂の思惟する部分はヌースからロゴスを受け取り、他の諸部分は思惟する部分からロゴスを受け取るのである」とされるのである。また、ロゴスを聞いて魂が変容することはなく、何の影響も受けずにこれを知るのだとする。
プロティノスはなかなか念入りな論者であって、今度は記憶についてもその考察に付け加えて、記憶の前後によって魂が変容するのではなく、ウーシアとして持つ、記憶という働きを可能態から現実態に活性化させたと説くのである。
一方、プロティノスは、われわれが感性界の出来事を強く意識することの妥当性を認める。が、しかし、「変容を受けるものがいったい何であるかを調べてみなければならない」として、魂が感性界の出来事に感応したときでも、やはり、それは魂が変容したのではなく、「魂は欲求したり、推理したり、思いなしたりしながら動く」と云われる時の「動」を取り上げて、「それらの動が魂自身から生じている」のだとするのである。
ここまできて、プロティノスは一旦もとの論に立ち戻って、魂の残りの「受動的な部分」と呼ばれているものが、本当に受動的なものなのかどうかを検証する。そしてこの魂の受動的な部分とは、諸々の情念が生ずるところではあるものの、その情念とは「思いなし」から生じるのであり、その、われわれが呼ぶ思いなしとは、「下位の領域のもつ漠然とした思いなしのようなもので、定かではない表象」であり、かつ「しかし、それらの表象から生じたものは、肉体の領域での混乱として、すでに感性的なものとなっているのであって」、ゆえに「そのようなことは、魂の部分には起こりえない」とされる。
導かれる結論は、「魂の受動的部分は、受動の状態の原因者ではあるが」、「魂の受動的な部分それ自体は、音階の調べに似て、平静を保ちながらとどまっている」と述べて、魂は全ての部分で受動的ではない、すなわち、変容することはないとするのである。
以上のように魂の非受動性について述べたあとに、これを根拠としてプロティノスは、素材の非受動性について考察する。
まずプロティノスは「物体は<より後なるもの>であり、<合成されたもの>であって、素材が他のものと一緒になって物体を作るのであるから、その素材は非物体的なものの部類に属する」と、素材が非物体的であることを言う。次に、素材は、「知性からの力を受け取っておらず、「有るもの」をまったく欠いているのであるから、逃げることさえもできない無力なものなのである」として、素材が無力な故に、形相の「影は、素材に作用を及ぼしているように見えるけれども、実際には、何の作用も及ぼしていないのである」と言う。そして「素材の方も抵抗する力を持っていないのだから、影は素材を切断することなく通るのであって、それは水を通るのに似ている」として、力を持たない素材に対して、「素材のなかにはいってくる影は、無力で弱く、抵抗する力を持ってはいない」と、両者が共に、プロティノスの言う、偽りであるゆえに、「どうしても『素材は非受動的である』ことを許さざるをえないことになるのである」という結論を導くのである。
この後、プロティノスは素材の非受動性について、様々な角度からその主張を補強する。例えば、「素材は作用を及ぼすものの影が映し出されるものである」や、「素材は大きさという性質は持たない」、「素材は大きさそのものでもない」、「例えば『大』は素材がまとう衣服のような形相の影」である、等。
ただし、これほど念入りにプロティノスが素材をネガティブに記述するのは何故か、という疑問に適切な答えは得られていない。ネガティブさを強調するのは意図的なものではないという考えもありえるのだが、今のところ何とも言えないのだ。
(2014/7/3)
■ III-7-(45)永遠と時間について (1.2Mb)
プロティノスは問う、「時間の内にあることが、しかもまたどうして(同時に)永遠の内にあることができるか」と。永遠は人間にとって身体的認識の外にあるから、逆に容易に定義できるのであるが、人間が感覚する時間と永遠の関係については自明ではないのである。そこで、プロティノスはこれに続いて、両者の並立について、「その前に時間(とは何か)が発見されて初めて知られうるだろう」と述べるのである。それでは時間をプロティノスはどのように考えたのだろうか。
そこで、「時間について述べられている諸説をおそらく三つに区分するのがよいだろう」として挙げられたのが、
- (1)時間は何らかの指定される動きであるのか
- (2)時間は動くものであるのか
- (3)時間は動きに関する何かであるのか
である。
(1)については、動きには開始と終息があって、そのどちらも時間という枠組みの中にあるので、時間そのものではない、(2)は天球の回転のようなものであるという主張であるが、天球の回転に早い部分と遅い部分があることからこれも時間ではない。天球のある部分の動く距離だという意見については、距離は時間ではなく場所であるという理由で却下される。(3)は、時間とはある特定の動きの数であるという考えである。だが、これも動きが無秩序なものであるなら数えることはできないし、すべての動きに共通な、数え得るものがなければならない。
すなわち、時代はガリレオの生まれる前であり、振り子の等時性は見いだされておらず、プロティノスの言うように、特定の何かを数えることが時間であるという考え方にまで至っていながら、確固たる秩序を保つ数えるべき対象物を発見できなかった故に、時間に対する考察はそこにとどまってしまうのである。そこで、プロティノスは時間の探求ではなくて、永遠についての考察から、時間を観るという方法に立ち戻るのである。
プロティノスによれば、時間は「自分がそれ(以前あるいは永遠)とともにオン(有るもの)の内で安らっていた。そのときはまだ自分は時間ではなくて、かのものの内で自分自身も静かに安息していた」。ところが、「余計なことの好きな本性がいて、自らが支配したいと望み、独立していること、現にあるよりももっと多くのものを求めることを望んで、それ自身も動き出し、自分(時間)も動きだした」というのである。それゆえに、時間は「永遠」の似姿でもあるのである。
ということなのであるが、では、現在の我々が認識している時間、それは等時性という言葉で表されるのであるが、その等時性とは何か、までに遡ると、時間とは何かについて我々が持つ知識と感覚とが完全に一致するかどうかについては、自明ではないように思われる。まず、等時性に対する我々の理解はどのようなものであるのか。ググると、どこにもほぼ同じような定義があって、
- ・振り子などの周期運動で、周期が振幅の大きさに無関係に一定であること。
- ・時間の間隔が一定で等しいこと。特に,周期運動の周期が振れ幅に無関係で一定な場合をいう
などと記述されている。「時間の間隔が一定で等しいこと」は、単語の説明であって、意味的には等時性の同義反復である。すると、周期運動の周期が(a)振幅に無関係で、(b)一定である、という論に還元されるのであるが、まず(b)一定である、という記述は、周期が一定であることが等時性であることそのままであり、これも等時性の同義反復である。では、(a)振幅に無関係に、という論を考えると、これは最も普通には振り子の振幅を指しているのであるが、当然ながらこれは物理的には微小な振幅の時にのみ成り立つのであって、ガリレオ程の観察者であれば、周期が振幅に関係していることは直ぐに見抜いたことであろう。とすると、ガリレオが確信したのは一体、何であるかということになる。
最もありそうなのは、一日の長さが厳密に、振り子のような「物理的過程」により、「数えられる」ということではなかったか。ガリレオが等時性を発見した時、振り子の周期を自分の脈拍と比較したというエピソードがあるというから、「数えられる」というのがキーワードであることに間違いはないだろう。
勿論、日にちを数えるというのは、古代から知られていたのである。それでは、時間について、ガリレオが気付いて、それに遡るプロティノスが疑問に思っていた点は何であろうか。最初に挙げられるであろうことは、一日という単位は数えられるのであるが、同時に伸び縮みするという事実である。すなわち一日を単位とするのは、時間が何であるかを考える上で必ずしも適当ではないし、プロティノスにとっても適当ではなかったのではないか。
もちろん、プロティノスがガリレオに劣るわけではなく、このときガリレオが。望遠鏡を以て天体観測をしたという点が、決定的に重要な両者の違いであろう。すなわち、望遠鏡は機械的に肉眼の能力を拡大するものであり、機械的なものを通じての認識が肉体のみによる認識と異なるものではない、という考え方をガリレオが持っていたのに対し、プロティノスの時代には、機械によって人間の感覚を拡大するという手段が、そもそも出現していなかった故に、「特定の動きの数であるとも考えらるが、動きとは無秩序なものであるから、時間は数えられない」という結論に至った点こそが、両者を分けたのであろうと考えられるのだ。
その結果、ガリレオにとって一日とは振り子の周期で数えられるものであり、プロティノスにとっては、われわれの感覚する時間というのは曖昧なもので、絶対的で唯一の「永遠」の似姿である、という結論に至るのである。というわけで、仮にプロティノスの云うプラトニズムが、キリスト教に流れ込んでいるとすると、ガリレオの考え方がキリスト教会に受け入れられ難いのは、理解できるし、さらに、その後、ガリレオの考え方は果たして容認されたのかどうか、という問題が残っているのである。というより両者が共存することはあり得ないし、ネオプラトニズムが根幹にあるとすれば、ガリレオの考え方は未だに許容されず、それがガリレオの立場にある者たちのキリスト教に対する態度に影響を与えているのではないか、とも言えるのである。
(2014/9/2)
p.s. 時間については近現代の哲学者がこれをどう捉えているのかという、私的な興味がある。例はいくつかあって、北嶋美雪は「プロティノスの時間論、プロティノス全集付録第3号第3巻、昭和62年5月」において、プラトンとプロティノスとアウグスティヌスをとりあげて、それぞれの時間論とその関係を論じている。
これによれば、プラトンは「『ティマイオス』に見られるように、時間は恒常不変でつねに一の内にとどまる『永遠』の写しとして、しかし数に即して円運動をしながら動く、『永遠を写す動く似姿』」と考え、プロティノスは、「水地氏の解説にあるように、『永遠から時間を考察し、かの世界から下降した世界魂の生の形態としての時間」を捉え、これは『時間とはある生活からある生活へとたゆみなく移行していく運動においてある魂(世界魂)の生である(III 7, 11)』から明らかであるとし、さらに、プロティノスとしては『知性界、すなわち永遠へと向き変わり、そこにやすらう(12節)』のが本来なのである」と特徴付けている。アウグスティヌスの時間論は、「(『告白』第11巻)29章に至って突如として『いくつかの方向への分散が私の生なのです』という句と共にdistentio(分散)の意味の転換がなされる。そして彼は『時間のうちに分散している私』が永遠存在たる一なる神のうちに『集められ』、『神のうちにとけこんでしまう』ことを切々とねがっている」などの例をあげて、「『告白』第11巻において、彼が『創世記』冒頭の解釈をめぐって生じた、『時間とは何か』のアポリアに直面し、神の授けを再三乞い求めながら辿り着いた答えは周知のとおり『(過去・現在・未来の三つの方向への)精神の延長(26章)』というものであった」として、ここからプロティノスとアウグスティヌスの関係を導いて、「ここに至ってはアウグスティヌスとの距離はわずかでろう。ただし後者(アウグスティヌス)の場合、何よりも個人の魂が問題とされるなど重要な相違があるのは無論である」としている。
さらに北嶋によれば「ボーマン(T.ボーマン、ヘブライ人とギリシア人の思惟、1956)がユダヤ、キリスト教の正統的な時間観(ベルクソン流に言うなら、『空間化された時間』とは区別された意識の『持続』として、純粋に継起そのものとして時間を捉えるのがヘブライ人の時間把握だということである)として賞揚するベルクソンの源流にあるのは言うまでもなくアウグスティヌスである」とし、ボーマンの論として「円環的であれ、直線的であれ、『アリストテレス、自然学、第4巻11章の『時間とはより先、より後という観点から見た運動の数である』に立脚したギリシア人も、またそれを受けついだヨーロッパの人々も、空間表象が先行しているために、時間を線の比喩で表象し、空間化している、否、せざるを得ないのであって、その点では両者は同列であるとした」というユダヤ・キリスト教的観点のあることを紹介している。
北嶋はこのボーマンの論を、O.クルマン(キリストと時、1948)や同じ見解を持つR.ブルトマン(歴史と終末論、1955、講演)が主張する「ギリシア人の時間把握が円環的であるのに対して、キリスト教の救済史における『時』は直線的であるという見解」を批判するものとしての紹介である。
私が興味を持つのは、近現代の哲学者の時間把握に、仮にアウグスティヌスを源流とするベルクソンの考え方が反映している、しかも強く反映されているとすれば、ガリレオの提示した時間が、「いまもなお、哲学者に受け入れられてはいないのではないか」という点にあるのだ。つまりヨーロッパの人々の間にある哲学が、時間を過去・現在・未来にわたる、魂の生すなわち「線で比喩される生の持続」であるとして、それが今に引き継がれているならば、近現代の哲学者にとって、未来が「分岐」するというような確率的時間論は、一顧だにされていないのではないか、という私の疑問があるのだ。
このあと、図書館に出かけてベルクソンについてざっと見てみると、「ベルクソン読本、久米 博、安孫子 信、中田 光雄・編、法政大学出版局、2006」と云うガイドブックがあって、新しい知見が得られた。本の紹介に「伝統的哲学への根本的かつ全面的な批判を展開して、サルトル、メルロ=ポンティ、ドゥルーズ、デリダ等々、20世紀の哲学に測り知れない影響をもたらし、現代思想の展開の軸となったベルクソンの思想を再検討し、ベルクソン・ルネサンスをめざすガイドブック」とあって、ここから、現代思想における時間把握について、ベルクソンと対比させることにより、その全体像がほぼ得られるのではないかと予想されること、また、ベルクソン自身がプロティノスについて研究していて、ベルクソンの考え方をプロティノスを通じて理解できそうだ、等である。
先走って言えば、ベルクソンやその他の現代哲学者群は、近代科学に接してはいても、その時間理解や、それに関連した事象の生起と確率、結果としての未来事象を確率的な嵩、あるいは事象の生起をグラデーションとして捉えることに、失敗しているのではないかという疑念が、大いに高まったのだ。
(2015/2/20)
■ III-8-(30)自然、観照、一者について (0.8Mb)
一者については、「素材についてII-4-(12)」、「グノーシス派に対して」II-9-(33)」のなかでも言及されているが、プロティノスはこの章において、より詳しい説明を試みる。プロティノスは一者を述べる前に、知性や生命やその活動などについて説明して、一者を表わすための慎重なステップを踏むのである。まず、知性や生命などすべてを含む「万有」が有るとし、万有は当然ながら多であるのだが、この万有のいずれでもない一者が万有の源であるとするのである。
この言説に対して、万有であるなら一者もそれに含まれるのではないか、という反駁に、プロティノスは、生起の順番によって反論する。つまり一者は万有に先立ってあるものなので、万有の源でありうるのだとするのである。ここで、後や先という順番、言い換えるなら時間の前後の概念が一者の説明にも有効であるというのは、プロティノスの暗黙の前提になっている。
このように一者を時間的に位置づけた上で、一者は、「これを源とする諸実在のいかなるものでもないのであって、存在でも実体でも生命でもなく」、これについて述べる言葉すらないすべてを超えたものとされる。それゆえに、「有る」ということもできない。そこで、「これに身を投じてそのなかに憩い、直感的にそれを理解し」、「その後に生じることになった諸実在を通してそれの偉大さを知り」と、プロティノスは続けて、感覚による理解を求めるのである。もちろんこれは「神への帰依」と言い換えることもできるのであり、キリスト教にぎりぎり近づいた表現であるとも言える。
さらにプロティノスは一歩進んで、一者の本質は善であることを言うのであるが、ここではいささか、回りくどい手順を踏むのである。まず、第二位のものである知性が、知性界の素材と一者から与えられた形相から成り立つものであり、それは観ることを本性とするものであって、常に活動するものであることが言われる。その本性に従って、知性はかつ知性は善を観ることによって充足されるとする。なぜ善を求め充足するかと言えば、知性の形相は一者から与えられているからである。
(2014//)
■ III-9-(13)種々の考察 (0.3Mb)
種々の考察と名付けられているように、それぞれが関連しているということは言い難く、また、叙述の順番としては13番目とされているように、エネアデス全体から見ると早い時期に書かれたものであることは確かなのだと思われる。従って、必ずしもプロティノスの思想が固まった時期とは一致しない可能性があるし、事実、マッピングしても、明確な構造が見えてこないのである。とは言っても、一者については多くの行数を使って説明されており、かつ一者が全ての議論の原点であるのは間違いないので、この記述が執筆された時点におけるプロティノスの一者についての考えに対して、この部分を別のエネアスにおける考察との関係において分析することは、プロティノスの理解に有効であろう。
さてプロティノスは言う。第一位のもの(一者)は欲求を持たないものである。なぜなら欠けるもののないものが何かを欲求する必要はないからである。さらに、理解する働きを持っていないのだと。つまり、何かを理解するということは理解する以前に何か欠けたものがあるからであり、第一位のものは完全なものであるゆえに、何も付け加えるあるいは取り入れる必要を持たず、それゆえに他を理解する必要がないのだと。また第一位のもの(一者)には自己意識という概念の有無を問うこともできないとも言う。なぜなら、意識を持って自己を意識するということは、その時点の先では自己自身を知らなかった、ということになってしまうからであり、完全なものとはならないからである。さらに、完全なるものとは善なるものである。善なるものが意識を持って、自己自身を善なるものと認めるならば、認めるより先には善はなかったことになるからである。それゆえに、第一位のもの(一者)に対して「生きる」という言葉を使ってはならないのだと、プロティノスは述べる。
その結果、第二位のもの即ち知性が、生きるものであり、第一位のものを、強く求める、すなわち欲求を持って観るゆえに、直知作用を持つのであり、そして善である第一位を欲求し直知することが、尊いというのである。
また第一位のもの(一者)は、動と静を産出することの可能な力であり、それゆえに動と静かからも超越しているのであると述べられる。この時点でプロティノスにおいて、動と静つまり、運動とは時間と如何なる関係にあるかが必ずしも明確に定義されていないので、動と静を産む力というのは、何時からあって、何時それらを産み、今はどのように在るのかが、結果として明らかではないのである。明らかにするためには時間が何であるかが示される必要があるのだが、それを明らかにする過程で、時間と第一位のもの(一者)との間にどのような関連があるのかが示されなければならない。つまり、時間について明らかにする必要があるのであり、従って、「III-7-(45)永遠と時間について」と「III-8-(30)自然、観照、一者について」と同時に読み解く必要があるのだ。
(2014/8/7)
■ IV-2-(4)魂の本質第一編 (0.3Mb)
"魂の本質とは何であるのか"で始まる、「魂の本質第一編」は、分割されない知性の眷属にありながら、感性界に降りて、分割し得る諸物体に宿る魂が、如何なる<ト・オン(有)>であるのかを述べるものである。プロティノスにとって、生物には魂が宿っていると考えるのが当然であるから、分割されることのない知性の類である魂が分割し得る物体に宿ったとしても、魂は分割されるものに変化することはない、という結論を導くための議論となっている。
感性界にある分割し得る諸物体に宿る魂が、本性では知性の眷属であるゆえに分割されない、という矛盾を解消するために、プロティノスは、諸物体に宿る魂は、一にして多であり、多にして一であるという、一見、アクロバティックな議論を提示するのである。
この編において、プロティノスはいきなり、「一にして多」を主張するのではなく、「一にして多」でなければならないことを説明するために、魂は物体であるとするストア派の主張に論駁するという形式を以てする。ストア派によれば、魂は人間の肉体に宿って、指導的部分と知覚する部分がそれぞれ肉体の定められた座にとどまり、指導的部分は知覚する部分から伝えられた感覚内容に承認をするのだと主張するのであるが、この主張に対してプロティノスは、指導的部分だけが知覚するとしても、指導的部分だけが知覚するのではないとしても、両方のばあいに矛盾が起きるして、その主張を否定するのである。
また一方で、魂が一なるものとしてとどまっているならば、魂は個別的な生きものの中心にあるとしても、生きもの全体としては魂のないままにほうっておかれることとなるとして、その考えも否定するのである。
こうして魂が生きものに宿った時、分割されるのでもなく、一なるものにとどまっているのでもないとするゆえに、プロティノスは、"自己自身が<多なる一>であることによって部分的なもののすべてに生命を与え、自己自身が<不可分な一>であることによってそれらを思慮深く導くのである"、とするのである。
(2014/10/27)
■ IV-1-(21)魂の本質第二編 (0.07Mb)
「魂の本質第二編」は、「魂の本質第一編」を補強する、ごく短い一編であり、魂の分割性と分割不可能性について述べる。プロティノスによれば、魂はあの世においては、知性と同じく、そのすべてが一体となって居を占めるのであるが、轂から輻が出るように、この世に降下して肉体に宿るので、本性上は分割されうるものであるとされる。
従って、魂はこの世にあっても上位の部分ではあの世を観ているし、全体者としてのあり方を保持してもいるのだという。さらに、「魂の本質第一編」の論を受けて、"魂は自らをこの世の物体に与えるのであるが、物体の全体に入っていくのだから、分割されてはいないし、物体のどの部分にもあるのだがら分割されてもいる"と述べられる。
(2014/10/28)
■ IV-3-(27)魂の諸問題について第一編 (1.9Mb)
(2014/10/28)
■ IV-4-(28)魂の諸問題について第二編 (2.6Mb)
(2014/12/6)
■ IV-5-(29)魂の諸問題について第三編あるいは視覚について(0.7Mb)
(2014/12/25)
■ IV-6-(41)感覚と記憶について(0.3Mb)
感性界に居るわれわれが感覚器官によって感覚するとは、何かについて、プロティノスは言う、「感性的なものの印影が魂のなかに生じて魂に刻印を残すのでもなければ、その印影が魂のなかで持続している時に記憶があるのでもない」と。すなわち、アリストテレスの説、「記憶は、魂のなかに印影がとどまることによって(成立する)習知や感覚知の保持である」という考えを取らないのである。
なぜ、プロティノスがそう考えたかといえば、魂は直知界とつながっているものであり、それゆえに全ての形相を含んでいるはずで、新たに何かが魂に取り入れられることはないというのが、その理由なのであるが、その他にも、「或るものの感覚知を得る時には、われわれは視覚対象を見、その方向に視線を投げかけている」とあるように、例えば視覚のばあいには、視覚対象から何かが来るのではなくて、われわれが視線を対象に投げかけているのだという理解があるのである。これについてはゲーテの「色彩論」が直ちに思い起こされるのであって、ゲーテによれば色彩とは、物理的な光とそれを観ずる感覚器官を通じた人間の主体的な認識との共同作業の結果であるというのであるが、逆に言えば、視覚とは対象物からやって来る光を受動的に受け取るのではなくて、われわれが主体的に視るゆえに対象が感覚されるという、プロティノスの考え方が、ゲーテにまで至っているとも言えるのではないか。
それでは、われわれの感覚知とは何であるかについて、プロティノスは、感性界において、われわれの魂は、感性的な対象を判別する力を最初から持っているのだとする。プロティノスによればそれは視覚にとどまらず、聴覚や味覚や臭覚も同様で、感性界の状態(タ・パテー)に対して魂はそれらに対する感性知や判断を持つのだというのである。しかしながら、プロティノスは魂が判断の力を持つというだけであって、感覚とは何かについてそれ以上は述べないのである。
感覚に続いてこれを記憶する働きとは何かについて、次にプロティノスは述べる。まず、対象が知性的なものであるばあいには、魂が感性界にあってもなお知性界につながりをもつゆえに、「知性的なものとかかわりを持つならば、記憶を呼び起こすことによってそれら知性的なものを直知する」という、所謂、想起説を述べる。次に感性的なものについては、感覚について述べられたように、感性的なものの記憶は魂の能力による感覚器官が捉えたものの持続である、とするのだ。プロティノスは述べる、「魂はそれに対して、あたかも自分のそばに現にあるものに対するがごとき状態を長時間にわたって持続することになるのであって、その力が強ければ強いほど、その状態も持続するのである」と。
結局のところ、プロティノスは、「…魂にかかわりのある事柄はすべて、人びとが…想定していることとは…ちがったあり方をしている…のである」としていて、感覚と記憶については、明確な説明がなされているとは言い難いのである。
(2015/3/14)
■ IV-7-(2)魂の不死について(1.1Mb)
(2015/1/17)
■ IV-8-(6)魂の肉体への降下について(0.5Mb)
(2015/1/20)
■ IV-9-(8)すべての魂は一体をなしているのか(0.3Mb)
(2015/1/25)
■ V-1-(10)三つの原理的なものについて(0.9Mb)
「三つの原理的なもの」というタイトルからは「三位一体」が連想されるが、訳注にあるように、本論の表題がプロティノス自身が付したものではない(ポルピュリオスによる「伝」4を根拠としている)とされているし、第8章の24行に「パルメニデスその人といえども、われわれの三原理に協調しうる者となるのである」とあるように、本編は「三位一体」とは無関係なことが解る。
それでは、三つの原理とは何かと言えば、プロティノスが何度も述べているように、「一者」が第一の原理であり、「知性」が第二の原理であり、「魂」が第三の原理である。
(2015/2/2)
■ V-2-(11)第一者の後のものたちの生成と序列について(0.2Mb)
(2015/2/)
■ V-3-(49)認識する諸存在とそのかなたのものとについて(1.5Mb)
(2015/2/)
■ V-4-(7)いかにして第一者から第一者の後のものが。および一者について(0.2Mb)
プロティノスは「一者」が「英知」を生み出すにあたって、それが「必然」であるとする。当然乍ら、そこにはプロティノスの考える「必然」という展開が、他の人にとっても妥当と認められるべきであるという前提があるのである。
現代ならば、その前提は、「正しい」という性質を持つものであるのか、あるいは多くの人の認識において「共通」という性質を持つものであるのか、のどちらかに場合分けされるべきである。勿論、プロティノスのいう「必然」という「展開」は、「正しい」としているのであって、彼の言う「必然的な展開」が誤っている可能性については、これを暗黙的に認めていないし、この「必然である」、を「正しい」とする見方は、この後に引き継がれていくのである。
さて、プロティノスは「一者」が「英知」を生み出すことは、「正しい」か「誤っている」かのどちらかで、「正しい」のか、どうして「誤っている」のかが明らかでないのは、認識する方法が適切でないのか、あるいは説明が不十分であるという方法論的立場をとる。つまり我々にとって問題と思えるのは、単に方法が適切でないだけであって、途中の認識の方法の如何を問わず、それを無視することのできる絶対的な「始原」があるのが「必然」であるとするのである。つけ加えるならば、方法論であればいつか「正しい」手順が見つかる筈であって、仮に手順が見つからないとすれば、それは方法によって辿りつくことのできない「不可知の領域」に問題があるとする。
結局のところ、「一者」は「不可知の領域」にあるのであって、そこから「英知」が生まれて、われわれの「認識」の源となるのである。繰り返せば、それは「必然」として「認識」されるというプロティノスの立場が出発点であることに留意しなければならない。(注)
なぜ「一者」が設定されたのかを考えれば、プロティノスの言う「一者」は勿論 ー 勿論とここで述べるのは、ギリシャ哲学者の生真面目さで、我々に魂があるから、その源である「英知」があるのであって、「英知」が「有る」なら、さらにその始原たる「一者」を求めなければならない、という、我々が認識できて、それゆえ存在すると考えられる魂の存在から遡って、「一者」に辿り着いた後にまたそこから下って ー 我々の魂の存在を導くためのものであることが分る。
この「一者」について、プロティノスは、「< 一つである >とそれに述語することすら虚偽であり、ロゴスも知識もこのものについては成り立たない」、物体的なものですらないものであり、「一」であるゆえに他を持たず自足したものであるとした上で、「それはすべての有るもののうちで最も力のあるもの」ゆえに、「自分の内で立ちどまっているということが、どうしてできよう」、そして「(一者以外に)何かが存在すべきだとすれば」、「(その)何かがかのものからも生まれねばならぬわけで」、「(生まれるのは)かのものからということは必然なのだから」という認識論によって、「一者」から「これらのもの」が生まれたことを「必然」の展開とするのである。
「一者」から生まれた第二位のものが「英知」であり、「直知」するものとなって、「直知」される「一者」に「向き直る」のである。「直知」するものであるから「一者」と相対化されて<エイナイ(有る)>とウーシアー(実有)となるのである。また、この「英知」から全てが生まれるゆえに、それは一にして多であるとされる。また「直知」することは「働き(エネルゲイア)」であって、「直知」する「働き」とともに、実体である「英知」から出る「働き」も持つとする。
こうして、かなたにあって完全に自足している善である「一者」と、それを「直知」することによって「働き」を持ち、「有る」ものとなった「英知」、という関係が、「神」と「キリスト」の存在を認識論的に証明するものである、と看做すことに至るまで直ぐである、というのは否定し難いもとのなっていくのである。
注:これに関しては、次章の「ヌースの対象はヌースの外にあるのではないこと、および善者について」の解説にある、「ヌースの対象はヌース自身の内に存在するというプロティノスの見解の、いわば認識論的証明である」の、「認識」論の前提であることに注意するべきである。なお、われわれの多くにとって「共通」して「認識」されるゆえに「必然」として「認識」されるという、私の立場は、基礎付け主義(foundationalism) 、整合説(coherentism) 、内在主義(internalism)、外在主義(externalism) 、信頼性主義(reliabilism) 、知識の因果説(causal theory of knowledge) 、決定的理由(conclusive reasons)、閉包原理(closure principle)、文脈主義(contextualism) (以上WikiPedia)のいずれにも当て嵌まらないようだ。
(2015/2/23)
■ V-4-(7)ヌースの対象はヌースの外にあるのではないこと、および善者について(1.1Mb)
(2015/2/23)
■ V-6-(24)有のかなたのものは直知しないこと、および第一義的に直知するものは何か、そして第二義的に直知する者は何かということについて(0.4Mb)
(2015/2/23)
■ V-7-(18)個物にもイデアがあるか否かについて(0.2Mb)
プロティノスはまず各人を各人とする魂は、世界魂と一部を共有しているのであり、また世界魂はこの世の生きものの全てに形相を与えている、ゆえに我々の魂も全ての形相を持っているのだと宣言する。
これに反するような例として、父と母から生まれる子は父と母のそれぞれの形相が混合されたように見えるが、一方、全く別の形相が与えられているとしても別に問題とはならないし、逆に、人間には同一のイデアが与えられていて、素材を支配する程度が異なるという観点に立つと、活発な美しい子供達の間には差と順位があることになってしまうと云うのである。ただし、醜悪さについては素材に対する形相の支配の程度が現れ得るとする。結論としては、個物は全て異なる形相が与えられているとされる。
着目すべきは、この論でプロティノスは時間について言及していていることで、宇宙の時間は円環的なものであり、英知がそれを知っていて、宇宙魂にはこの時間に必要な形相の分量が与えられていて、その形相が尽きた時にまた新しい時間が始まるのだとしているのだ。従って、宇宙魂の持つ形相は無限といってよい程であるが、英知はそれを、形相の無限性として、全て把握しているのだする。
(2015/3/4)
■ V-8-(31)直知される美について(1Mb)
解説によれば、本編はゲーテによりその1章が翻訳され、ライプニッツの「単子論」には、本編特にその4章に相似する思想が見られるとしている。つまり、本編は、後世の哲学者の興味を多いに惹いたのだと推定できる。では、どこに彼らは惹かれたのであろうか。
(2015/3/3)
■ V-9-(5)ヌースとイデアと有について(0.7Mb)
■ プロティノスの有るものの類についてVI-1~3
VI-1-(42)プロティノスの有るものの類について第一篇(2Mb)
VI-2-(43)プロティノスの有るものの類について第二篇(1.5Mb)
VI-3-(44)プロティノスの有るものの類について第三篇(1.8Mb)
解説によって、
「この作品の目的は、まずアリストテレスの『カテゴリー論』と題されている作品に焦点をあてながら、アリストテレスがそこで『カテーゴリアー』という名称で紹介している十個の最高類を批判的に吟味し、プラトンの最高類の妥当性と、逆にアリストテレスの最高類の不当性を明らかにしながら、プロティノス自身の考える感性界の最高類を明らかにすることにある」
と紹介されているように、まずこの論は、アリストテレスの「カテゴリー論」を理解し把握していることを、読者に要求しているのであるゆえに、プロティノスの思考を辿るだけでは、不十分な理解とならざるを得ないのである。
アリストテレスの「カテゴリー論」
岩波版のアリストテレス全集、『カテゴリー論』第四章 には、
どんな結合にもよらないで言われるものどものそれぞれが意味するのは、あるいは「実体」か、あるいは「なにかこれだけ」(量)か、あるいは「何かこれこれ様の」(質)か、あるいは「或るものとの関係において」(関係)か、あるいは「或るところで」(場所)か、あるいは「或る時に」(時)か、あるいは「位している」か、あるいは「持っている」(所持)か、あるいは「為す」(能動)か、あるいは「為される」(受動)かである。
しかし、実体というのは、大ざっぱに言って、例えば人間、馬。「何かこれだけ」は例えば二ペーキュス、三ペーキュス。「何かこれこれ様の」は例えば白い、文法的。「或るものとの関係において」は例えば二倍、半分、より大きい。「或るところで」は例えばリュケイオンにおいて、あるいは市場において。「或る時に」は例えば昨日、昨年。「位している」は例えば横たわっている、座っている。「持っている」は例えば靴をはいている、武装している。「為す」は例えば切る、焼く。「為される」は例えば切られる、焼かれる。
しかし上に挙げられたものどもは、それぞれがそれ自身としてただそれだけで言われることは、どんな肯定においても存しない、いや、これらのものどもの相互の結合によって肯定はできるのである。というのは肯定はそのすべてが真であるか、偽であるかと思われるのに、どんな結合にもよらないで言われるものどもの何ものも(例えば、人間、白い、走る、勝つ)、真でもなければ、偽でもないからである。
のように、10種のカテゴリが提出されている。また、解説(松永雄二「世界古典文学全集16『アリストテレス』筑摩書房167p)によれば、
「われわれは、たとえば白さというものが存在するといい、また六尺というものが存在するといい、さらに人間が存在するという。ところで以上のおのおのが存在すると語られる場合、それらはまったく同じ意味で語られているのであろうか。それとも、その意味は多義的であり、つまりそれぞれの場合に、それらが『存在する』という仕方は異なるのではなかろうか。すなわち、たとえば人間は、『実体』として存在するものであり、六尺というものは、『量』として存在するものであり、白さとは、『性質』として存在するものではなかろうか。
アリストテレスにとって、『カテゴリア(範疇)』と呼ばれるものは、以上のような仕方で、およそ存在するものがそのいずれかに属すべき、いわば『存在するものどもの最高類』として、何よりもまず把握されるべきであろう。
してみると、そのような範疇=最高類は、はたしていくつあるのか。そしてそのそれぞれの範疇が持つべき、固有の領域とその特性とは、何であろうか。さらにはまた、それらのさまざまな範疇のうちで、とりわけ『実体』と呼ばれるものが、他の一切のものの存在主体としての資格をもつのは、何故であろうか。つまり換言すれば、『量』とか『性質』などに属するものは、いったい如何なる意味で、みずからがそれにおいてある基体として、『実体』への依存ということを必要とするのか。」
と概略されるのである。
「カテゴリー論」と述語
「カテゴリー論」を理解する上で、「主語」と「述語」の関係とその表現に注意する必要がある。
そもそも、AはBであるという記述について、これを"predicate"(であると断定する)という動詞から"predication"を通じて「カテゴリ」を説明する方法と、「Bである」ということを、「述語」という名詞から「述語する(注)」という動詞を新規に作り出すことによって「カテゴリ」を説明する方法の間に若干の食い違いがあるのである。まず、以下のように"predication"は説明される。
Predication
A subject (hupokeimenon) is what a statement is about.
A predicate (katêgoroumenon) is what a statement says about its subject.
Examples:
This (particular animal) is a man.
Man is an animal.
This (particular color) is white.
White is a color.
The same thing may be both a subject and a predicate, e.g., man and white above. Some things are subjects but are never predicates, e.g., this (particular) animal, or this (particular) color.
"Predication and Ontology: The Categories"
(http://faculty.washington.edu/smcohen/320/cats320.htm)
この上で、「カテゴリー論」の第2章を説明する、日本語と英語(Wikipedia)を比較すると、「述語」と"predicate"、「述語する」あるいは「述語になる」と"predication"の関係がより明らかとなる。
表現方法には、
結合無し(単語)による表現 (例:「人間」「牛」「走る」「勝つ」)
結合(文)による表現 (例:「人間は走る」「人間は勝つ」)
の2種類がある。
概念の内、あるものは、
1. ある「基体[5]」(主語)についての述語になるが、いかなる「基体」(主語)の内にも無い。(例:「人間」は、「特定の人間」(基体)の述語となるが、どの「基体」の内にも無い)
2. ある「基体」(主語)についての述語にはならないが、「基体」(主語)の内にある。(例1:「特定の文法知識」は、「霊魂」(基体)の内にあるが、いかなる「基体」(主語)の述語にもならない、例2:「ある特定の白」は、「物体」(基体)の内にあるが、いかなる「基体」(主語)の述語にもならない)
3. ある「基体」(主語)についての述語になると共に、「基体」(主語)の内にある。(例:「知識」は、「霊魂」(基体)の内にあり、「文法的知識」(基体)の述語となる)
4. ある「基体」(主語)についての述語にならず、「基体」の内にも無い。(例:「特定の人間」「特定の馬」)
Categories (Aristotle)
Next, he distinguishes between what is said "of" a subject and what is "in" a subject. What is said "of" a subject describes the kind of thing that it is as a whole, answering the question "what is it?" What is said to be "in" a subject is a predicate that does not describe it as a whole but cannot exist without the subject, such as the shape of something.
The latter has come to be known as inherence.
Of all the things that exist,
1. Some may be predicated of a subject, but are in no subject; as man may be predicated of James or John, but is not in any subject.
2. Some are in a subject, but cannot be predicated of any subject. Thus a certain individual point of grammatical knowledge is in me as in a subject, but it cannot be predicated of any subject; because it is an individual thing.
3. Some are both in a subject and able to be predicated of a subject, for example science, which is in the mind as in a subject, and may be predicated of geometry as of a subject.
4. Last, some things neither can be in any subject nor can be predicated of any subject. These are individual substances, which cannot be predicated, because they are individuals; and cannot be in a subject, because they are substances.
プロティノスの論述とアリストテレスの「カテゴリー論」との関係について
このプロティノスの論を解釈するにあたっては、若干のしかし本質的な問題が存在する。まず、前出の松永は、「カテゴリー論(範疇論)」について、そのアリストテレスの哲学における位置づけについて、解説に以下のように述べる。
「たとえば、いわゆる『概念』ー『命題』ー『推論』という安易な方式のもとに、一連の論理学的な著作を、かの『アナアリティカ・プリオーラ(分析論前書)』を頂点とする形式論理の確立という線上においてのみ把え、その最初の書物である『範疇論』をそのような枠内で『概念』論として把えることは、決定的に不当である。なぜなら初めに語られたように、『範疇論』の主題は一貫して、『存在するもの』のあり方にかかわるのであり、従ってそれはいわば本質的な意味で、アリストテレスの全存在論の基礎を形づくっているからである」
と。つまり問題というのは、解説に、
「…プロティノスにとっては…プラトンが『ソピステス』のなかで、『形相を[生成]に対する[有]』と解し、『形相(類)のうちで最も重要と言われているもの』として『有』『静』『動』『同』『異』を取りあげているのを見た時、プロティノスがアリストテレスの十個の範疇を生成界(感性界)の最高類と解して、これを『有るものの類』という観点から論駁し、プラトンの説く最高類こそ真であると解したのも、もっともなことであろう」
と述べられているように、プロティノスが意識的あるいは無意識的に、プラトンの説く最高類を正当化するために、アリストテレスの「カテゴリー論」を、プロティノスの解するプラトンの説に、いわば無理矢理にあてはめているところにあるのである。
「形相」に対する批判へのプロティノスの反駁と「カテゴリー論」
そもそも師プラトンの「形相」に対する批判的立場から、論述を展開したアリストテレスの「カテゴリー論」に論及するのであるから、論及の前に「形相」に対する批判である、「形相の分割」と「第三者」の問題を予め解消したと考える、プロティノスの立場を考慮しなければならない。
まずは、プラトン自身の提出した自己批判について述べよう。プラトンは「パルメニデス〜イデアについて〜」において、そこに、パルメニデスとソクラテスの対話を再現することで、自らのイデア論に対して批判を加える。その第一がイデアの分有から導き出される矛盾である。
議論2
「しかしまあそれはそれとして、どうかぼくに次の点を答えてくれたまえ。つまりきみの主張だと、何か形相といったものが存在するときみには思われるというのかね。そしてここ(われわれの周囲)にあるもの、すなわち形相とは違う他のものは、その形相を分取することによって、その形相が持っている呼称を[自分たちも]もつようになる。例えば<似>を分取することによって似、<大>を分取すれば大、<美>や<正義>を分取すれば正あるいは美となるというのかね」
「ええ、すっかりその通りです」とソクラテスが答えた。
「してみると、ソクラテスよ」とかれは言った。「形相そのものが部分に別れてあることになる。そして形相を分有するものも、形相の部分を分有することになるだろう。そして各々のもののうちに内在しているのは、もはや全体ではなくて、各形相の部分であるということになるだろう」
「ええ、そう見えます、少なくともそういうふうに見る限りは」
「すると、ソクラテス、そもそもきみが主張しようとするのは、われわれにとっては一つのものとしてある形相が、本当は部分に分けられるということなのかね。そしてそれでも形相はなお一つのものなのだろうか」
「いいえ、けっして」と言った。
こうして、プラトンは、形相が素材に与えられて認識の対象が現れるとする、「イデア論」に自ら批判を投げかけるのである。すなわち、イデアの分有があるとすれば、イデアが単一のものであるということと矛盾し、イデアの分有がないとすれば、認識の対象が多ではあり得ないという矛盾が導かれるという、所謂「イデアの分有」による「イデア論」批判である。
次に、プラトンはこの自己批判に、さらに反論を準備する。「イデアの分有」論により導かれた矛盾を、「似像」の導入によって解消しようとするのである。
議論4
「むしろパルメニデス、次のようなことになるのだと、わたしにはいま至極はっきりと見えているのです。つまりこれらの形相は、ちょうどお手本(原型)のようなものとして、自然のうちに不動のあり方をしているのであって、それ以外のものはこれに似たあり方をするもの、複写物(同じように似せてつくられたもの)としてあるのだということです。そしてこの限りにおいて、形相に対する他の事物の分有(共有)関係というのは、他の事物が形相に似たあり方をさせられる(似せられる)ということにほかならないということになるのです」
として、素材に与えられるのは「形相」そのものではなく、その「映像」のようなものであるゆえに、「形相」は「似像」として現れるのであるとするのである。だが、プラトンはさらに、自己に対する反論を用意して、次のように述べるのである。
議論4
「すると、いまもし何かが」とかれは言った。「形相に似ているとしたら、その形相の方がその複写物(似せてつくられたもの)に類似していないということがありうるだろうか、とにかくそれに類似するものとして複写された限りにおいてだがね。それとも類似しているものが類似しているものに類似していないなんて法があるだろうか」
「ありません」
「ところで、その類似している方のものが類似している他方のものと同じ一つの形相を共有(分有)するということは、大いなる必然ではないのか」
「必然です」
「そしてそれら類似するものが、それを共有(分有)することによって類似していることになる当のものとは、ちょうどかの形相そのものであるということになるのではないか」
「まったくその通りです」
「したがって、何かが形相に類似するということも、不可能ということになる。そうでないと、形相のほかにいつもまた別の形相が立ち現れることになるだろう。そしてまたその形相が何かに類似するとなれば、またもや別の形相がということになるだろう。そして形相が自分を分有(共有)するものに類似することになりさえすれば、いつも新しく形相が生ずることになって、いつまでもけっしてやむことはないだろう」
この反論は、後にアリストテレスによって「第三人間論」として定式化されるのであるが、実は同様の反論が既に述べられていて、上の議論はその繰り返しであるとも言える。
議論3
「ところで、その<大>自体とそれ以外のもろもろの大だが、これらを[大自体ももろもろの大も一括して]今と同じように向こうにまわして心で見るとしたら、どうなるかね。そこにまた、これらすべてが大と見られる所以の、何か一つの<大>といったものが現れて来ることになるのではないかね」
「かも知れません」
「してみると、もう一つ別の<大>の形相が立ち現れて、すでにこれまでにあった大自体とこれを分有している[もろもろの大なる]ものとの外側に並ぶということになるだろう。そしてさらにまたこれらすべての上にもう一つ別の形相が現れ、今度はこれによってそれらすべてが大であることになるだろう。そしてだ、きみのいう形相なるものは、どれももはや一つではなくて、むしろ無限に多いということになるだろう」
この自らの反論に、プラトンは直接的な答えを用意していないのであるが、上述の「同じように向こうにまわして心で見るとしたら」が、一つのあるいは、プロティノスにとっての答えの糸口となるであろう。それは、認識される対象は、知性界から映し出された形相により、感性界で認識されるのであるが、それを認識する魂も、感性界において、知性界の末端としてあるゆえに、対象を直ちに認識する、すなわち「直知」ことができる、という議論である。
『国家』第6巻508c
「目というものは」とぼくは言った、「君も知っているように、もはやこれを、白昼の光が表面の色どりいっぱいに広がっているような事物には向けずに、夜の薄明かりに蔽われている事物に向けるときには、ぼんやりとにぶって、盲目に近いような状態となり、純粋の視力を内にもっていないかのようにみえるものだ。」
「大いにそのとおりです」と彼。
「けれども、思うに、陽光に明るく照らされている事物であれば、はっきりと見えて、同じその目の内に純粋の視力が宿っていることが明らかになるのだ。」
「たしかにそうです」
「それでは、同様にして魂の場合についても、次のことを心に留めてくれたまえ。――魂が、<真>と<有>が照らしているものへと向けられてそこに落ち着くときには、知が目覚めてそのものを認識し、その魂は知性をもっているとみられる。けれども、暗闇と入り混じったもの、すなわち、生成し消滅するものへと向けられるときは、魂は思惑するばかりで、様々の思惑を上へ下へと転変させるなかで、ぼんやりとしかわからず、こんどは知性をもっていないのと同じようなことになる」
「たしかにそういうことになります」
「それでは、このように、認識される対象には真理性を提供し、認識する主体には認識機能を提供するものこそが、<善>の実相(イデア)にほかならないのだと、確言してくれたまえ。それは知識と真理の原因(根拠)なのであって、たしかにそれ自身認識の対象となるものと考えなければならないが、しかし、認識と真理とはどちらもかくも美しいものではあるけれども、<善>はこの両者とは別のものであり、これらよりもさらに美しいものと考えてこそ、君の考えは正しいことになるだろう。これに対して知識と真理とは、ちょうど先の場合に、光と視覚を太陽に似たものとみなすのは正しいけれども、それがそのまま太陽であると考えるのは正しくなかったのと同じように、この場合も、この両者を<善>に似たものとみなすのは正しいけれども、しかし両者のどちらかでも、これをそのまま<善>にほかならないと考えるのは正しくないのであって、<善>のあり方はもっと貴重なものとしなければならないのだ」
すなわち「第三の人間」の必要性をなくするために、プロティノスは、この<善>こそ、「一者」そのものであって、そこから一方向的に流出したイデアにより知性界が作られ、その知性界の魂が感性界に降下することによって、感性界における「知性」すなわち対象を認識する「人間」が作られたのだとするのである。
それゆえに、「形相」の感性界への実現は映像としてあるのであって、その反対の方向、すなわち、感性界の映像が知性界の「形相」に似ているかどうかは、「一者から形相が一方向的に流出しているがゆえに」、感性界に有るものにとっては知るすべがないのであり、唯一、知性界から降下してきた魂のみが、それを「直知」するのであって、「第三の人間」が、知性界の「形相」と感性界の「似像」の両者が「似ている」かどうか、あるいは「形相」の映像が分有されたものかどうかを、認識し判断する必要はないのである。
もちろん、その反作用として、感性界から知性界を知ることは、できないことになるのであって、ただ、知性界に未だ繋がっている魂のみが、知性界に戻る可能性を持つだけなのである。いわば、絶対的に、かつ「形相」を流出させる静的な「一者」が必須となるのであって、われわれ人間にとって感性界にある限り、「一者」の存在は「直知」によってのみ、あるいは感性界の諸々を捨象して残されたものが「形相」の「映像」であるとする、間接的な手段によってしか、認識し得ないということになるのである。
当然ながら、プラトンのいう<善>とは何かという問いに対して、プロティノスが「一者」を設定したことにより、それは感性界の人間には到達できないものとなって、アリストテレスの言う「最高善」とは大きく異なるものとなるのである。だが、一方、プロティノスの生きた時代において、ますますその勢いを増すキリスト教に対しては、その哲学的バックボーンとなり得る可能性を高めたとも言えるのである。
アリストテレスの「カテゴリー論」に対する論駁
以上の事前準備の上に、プロティノスのカテゴリー論について述べてみよう。
プロティノスの記述はカテゴリー論の詳細な吟味から始まる。立場は異なっても、アリストテレスの記述の解説と言っても良いのではないかと、思われる程である。
最初にプロティノスが吟味の対象とするのは「類の一つとしての実体」であるが、アリストテレスの記述が簡易に過ぎるために、プロティノスの論はアリストテレスの論に反駁するというよりは、「実体」に係るそれまでの哲学者の論のレビューのようになっている。すなわち、プロティノスの時代には既に、アリストテレスの云う「第一義的な実体」と「第二義的な実体」に係る論考が、不十分なのか、あるいは失われているのか、プロティノスも、アリストテレスの云う「類としての実体」を吟味するに十分な資料を手にしていないことが分る。
次に「類としての量」について、アリストテレスが『カテゴリー論』においては、「時間が量であるから、動も量である」とみなしているのである」としているのであるが、『自然学』においては「時間はその連続性を動より得ているから量なのであろう」と述べていることを指摘した上で、すなわち、ここでもアリストテレスの説明が不十分であることを示した上で、論述を続けるのである。プロティノスはここで「量」そのものではなく、「数こそ第一義的な量である」というアリストテレス学派の主張に論駁して、「事物のなかに見出される数は、数それ自体とは名称以外に何ら共通点を持ってはいない」と結論づけ、さらに時間についても、プロティノスは「時間は決してポソテース(量そのもの)ではない」と結論づけるのである。
関係(σχέσησ)については、プロティノスはまず、「関係」そのものが存在するかどうかという議論から始めて、存在する場合に、それは「超過と過少を表すの」なのか、あるいは、「作用を及ぼすものと及ぼされるもの」なのか、さらには「似ている似ていない」なのか、というふうに話を進め、そこにわれわれの判断というものが入っているのではないかと、疑問を呈し、
準備中
■ 有るものは同一のものでありながら、同時に全体としていたるところに存在するということについて
VI-4-(22)プロティノスの有るものの類について第一篇(2Mb)
VI-5-(23)プロティノスの有るものの類について第二篇(1.5Mb)
注目すべきは、この「有るものの類について」の最後の章に、プロティノスが、一者すなわち有るものを「神」と呼んでいることで、まるでプロティノスの信仰告白ともとれるような内容のあることである。既に述べたようにプロティノスがキリスト教について深く知っていながら、それに言及することを注意深く避けてきているのに、ここに至って、このような記述があることは、その後のネオ・プラトニズムがキリスト教に深く入って行く事を考えると、プロティノスの内面について慎重に吟味する必要のあることが示唆される。
■ VI-6-(34)数について(1.5Mb)
■ VI-7-(38)いかにしてイデアの群が成立したか。および善者について(3.1Mb)
■ VI-8-(39)一者の自由と意思について(1.6Mb)
最高位にある一者に意思はあるのか、つまり、多であるわれわれに自由意志があるのかどうか、なりゆきでわれわれがあるのではないか、という問いかけに対する、プロティノスの回答である。
一者は一であって、それ自体で充足してあるもので、彼が(一者は呼びようがないので彼と呼ぶのである)意思を持っているのかどうか、われわれにとっては計り知れないのであるが、プロティノスは、一者が生み出したヌースすなわ直知が、多であることを手がかりに論を進めるのである。
ここでも、プロティノスは一者とキリスト教の神の安易な同一視を完全に避けようとする。それは「彼(一者)がすべてをなし能うことを容認するとはいえ、そのばあいの『彼次第である』とは何を意味するかということを、あえて探求しなければならない」という、最高位の神であっても、われわれが探求する対象とし得る、とする態度に現れている。
■ VI-9-(9)善なるもの一なるもの(1.1Mb)
解説によれば、本編はプロティノスが九番目に書いた論で、「われわれの魂を導いて善者あるいは一者に合一させる方法について、彼が初めて説明した論文である」と紹介されている。しかしながら、一者の前に、われわれが遭遇するであろうヌース(英知)との間に、われわれが、どのような関係を結ぶべきかが述べられていないゆえに、この節は結論を急ぎすぎてはいないか、との懸念があるのであって、プロティノスの論にしては、議論の展開が早すぎるのではないかと思われるのである。
もちろん、プロティノスにとって、人の最後の目的は魂の一者との合一であるから、解説にあるようい、ポルフュリオスがこの論を、エネアデスの最後に置いたことに不思議はないのであるとも言えるのであるが。
2016.1.19
top