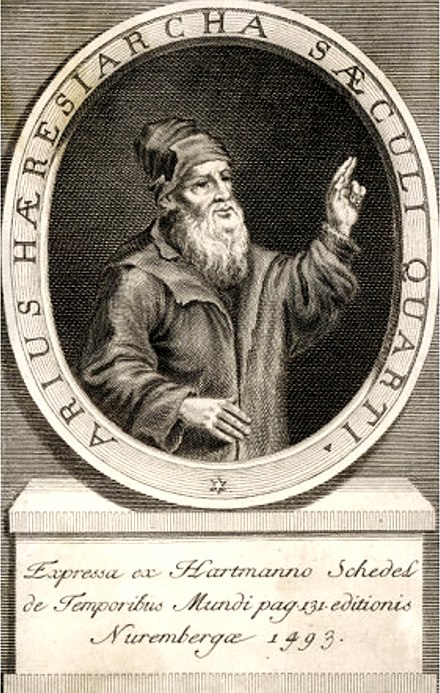■ キリスト教歴史二次元図(pdf size:2.2MB)(2014.3.10〜)
「中世思想原典集成」と「新カトリック大事典」から抽出し再構成したキリスト教の歴史をマッピングしたものだ。所々ではWikipediaを援用している。全ての論文に目を通した後に完成する筈のものであるが、時々の作業進展具合のスナップショットとして掲載し改訂する予定である。
ところで「中世思想原典集成」であるが、上智大学編ということから分るように、現在の正統キリスト者の著であるので正統の立場で記述されているところが興味深い。依然として異端者に対しては厳しい態度で記述されているのだ。例えば、最初のキリスト教徒皇帝であるコンスタンティヌス I世(306-337)に対する記述態度と、新プラトン主義のユリアヌス帝(361-363)に対する記述態度がまるで違うのだ。背教者ユリアヌスなどと呼び捨てにされている。
私はキリスト教徒ではないので、ここでは、異端とされる教えを無視することはしない。丁度、生物の進化における系統樹のようにキリスト教も分岐を繰り返して現在に至っているのだが、分岐した後、異端とされた教えを知る事によって、その成立過程を理解する上で、より理解を深めるための手だてとなると考えたからだ。ただし問題があって、異端という名前が如実に示すように、正統でないされた教えについてはその情報にフィルタがかかっているので、本来何を言わんとしていたのか類推するしかない。しかし、まるで汚らわしいもののように記述されている教えを読み解くのもまた興味深い。
その後、マップに書き込む時代が進んできてフランク王国のあたりまでくると、確かにヨーロッパの歴史の理解のためにはキリスト教の理解が絶対的に必要であることが確信される。日本の教科書のように宗教に対して一歩引いたような姿勢では全く切り込むことができないのである。イスラムの話もマップに表れてマップ自体がますます巨大化しつつある。
リヨンのエイレナイオス(130-200)の著である。ユダヤ教聖書をキリスト教の立場で解釈し説明する。
いきなりだが、アブラハムさ、サラの女奴隷に子供生ませておいて、サラに子供ができたからったって、その女奴隷と子供を砂漠に追放するってどうなの。おまけにその子供がアラブの始まりって。

Clemens Alexandrinus
アレクサンドレイアのクレメンス(150-215)の著である。クレメンスはアテネの裕福な家庭に生まれたと云われている。この論では、キリスト教が富裕層にまで拡大しつつある時、富者に冨を捨てる必要はないことを説く。現代の金持ちに説教するための論としてもおかしくない程で、教養あるクレメンスの人間性が感じられる。
同じくアレクサンドレイアのクレメンス(150-215)の著である。ギリシア哲学に精通していた著者が、キリストの教えにギリシア哲学が奉仕するべきことを述べる。
ローマのヒッポリュトス(170-235)の著である。唯一の神が様々なモドウス(様態)をとって現れたとするモナルキア主義に対して反駁し、三位一体を強調するもの。

Origenes Adamantius
アレキサンドレイアのオリゲネス( Ὠριγένης:185-254)の著した創世記をキリスト教徒の立場から見た講話である。二千年近くも昔の人なのに、その論を読むとひととなりが分る気がする。カッパドキアの三教父の祖師であり、天父受苦説を唱えるサベリオス主義に反駁を加えた、三位一体説を支持する教父。
■ グレゴリオス・タウマトゥルゴスの「テオポントスへ」(1)
グレゴリオス・タウマトゥルゴス(ρηγόριος ο Θαυματουργός :213-270)の著である。黒海沿岸ポントス地方生まれカッパドキア教会の創設者である。タウマトゥルゴスとは奇跡を行う人の意味である。受苦説に反駁を加える論。

Icône de saint Athanase
アレクサンドレイアのアタナシオス(296-373)の著である。ロゴス(言)すなわちキリストは神の被造物であり神と同質でないとするアレイオスを教会会議で破門した人物である。ロゴス自体、ギリシア哲学からの引用であるがキリスト教では、イエス・キリストを指す。この論では、ギリシア人のキリスト教批判に反駁する。
アレイオス (256-336)派と反アレイオス派は、ローマ皇帝の権力と絡み合いながら長い論争と互いの破門と断罪を繰り返した。この複雑な争いを「中世思想原典集成」と「新カトリック大事典」を元に私が図に表したものである。結局、アレイオス派は異端とされ、ニカイア信条においてαναθεματίζει ΄η καθολικη εκκλησία「公同なる教会は(彼らを )呪うべし」とまで言われることになる。
カイサレイアのエウセビオス(263-339)は、オリゲネス的従属説の神学的傾向のため、アレイオスに対しては同情的であり、ニカイア公会議(325)において採択されたホモウーシオス信条に対しては、ホモウーシオスという語が既に異端として断罪されていたサベリオス主義に通じるとしてその使用に反意を示したという。この論ではギリシア人のキリスト教に対する批判に反駁する。ギリシア人がその教養ゆえに尊敬されていたことがよく理解できる。
エルサレムのキュリロス(315-?)の著。洗礼の儀式順序を示す。

A Coptic icon, showing, in the lower left,
St. Anthony with St. Paul the First Hermit
アレキサンドレイアの司教であったアタナシオス(296-373)が、砂漠の聖者と呼ばれるアントニオスの伝記を著したもの。アントニオスは臨終に際しアタナシオスから贈られた衣服を返すように弟子に指示する。伝説ではアントニオスは105才の長寿を全うし、それまで修行は単独であったものをアントニウスの周りに修行者が集まったことで結果として修行者の集団である修道院の原型を作った聖人として名高い。
亡くなった後、聖アントニオスの伝記を書いたアタナシオスもアントニオスが葬られた場所は知らないと記したのに、その後6世紀半ばに墓所が発見されてアレクサンドリアに運ば れ、その後、コンスタンティノポリスへ、11世紀には南フ ランスのモット・サン・ディディエ修道院へ、さらに15世 紀末、南フランス、アルルのサン・ジュリアン聖堂に移された。聖アントニオスが数々の奇跡を起こしたということもあって、崇敬されている故だとも言えるが、本人からすればかなり迷惑と思われる死後の経緯を辿っている。

ナジアンゾスのグレゴリオス
ナジアンゾスのグレゴリオス(325-390)はカッパドキアの三教父の一人。アレイオス派をサベリオス主義としてその説に反駁した。この論では、サベリオス主義に反駁しつつ、父と子と聖霊の三位一体を述べる。
ナジアンゾスのグレゴリオス(325-390)の著。三位一体説の立場からキリスト単性説に反駁する。
バシレイオス(330-379)はカッパドキアの三聖人の一人。この書簡では三位一体説の立場からユダヤ教を批判する。
■ バシレイオスのヘクサエメロン(創造の六日間)について(2)
バシレイオス(330-379)の著。この論は天地創造が神の手によるものとしてギリシア人を批判する。
■ ニュッサのグレゴリオス教理大講話(2)(2010.10.18)
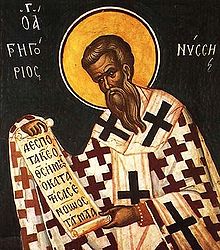
Icon of St. Gregory of Nyssa
ニュッサのグレゴリオス(335-394)の著。グレゴリオスはバシレイオスの弟でありカッパドキアの三教父の一人である。他教徒からの反論あるいは問いに対する答えという形式で三位一体説を説明する。洗礼の意義について詳しく述べているので、キュリロスの洗礼志願者のための秘技教話と合わせて読むと洗礼についての理解が深まる。
p.s. (2014/3/6)
この節を書いた時点ではマップの作り方が不十分であった、と反省しているので、時期を見て書き直したい。
■ ノウァティアヌスの貞操の賜物について(2010.11.12)
ラテン語を主たる著述に用いた神父たちの言葉、逆に言えばギリシア語ひいてはギリシア哲学についてのバックグラウンドが必ずしもあるとは限らない神父たちの著作とも言えよう。
■ ティルトゥリアヌスの洗礼について(2010.11.13)
洗礼に対する信徒の疑問に答えるものである。小児に対する受洗は遅らせるべきである、女性たちへの洗礼は女性が授けるとしても女性に積極的な権能を与えるべきではない、洗礼を失ったときつまり棄教者が再びキリスト教徒になるためには、血の洗礼すなわち殉教しかないなどと述べる。
■ ティルトゥリアヌスの殉教者たちへ(2010.11.30)
西方教会においてはギリシア語における信仰の「秘義」を指すものとして、ギリシア語からそのまま転化したmysteriumのほかにsacramentumが使われるようになった。mysteriumは原義の通り秘められた真理としての秘義を示すものとして使われたが、sacramentumは祭儀上の秘跡や典礼を意味するようになった。一方sacramentumはローマ軍兵士の誓約としての「旗の誓い」を意味していたので、キリスト教徒が神の兵士であるという連想をもたらす結果となった、と云う。ティルトリアヌスはカルタゴの司教であり、ギリシア的素養は持っていない。ギリシア教父とラテン教父との違いが明らかに認められる。
■ キュプリアヌスのカトリック教会の一致について(2010.12.17)

Thascius Caecilius Cyprianus
キュプリアヌスもカルタゴの司教である。この頃、デキウス帝によるキリスト教禁令が発布され、信者のみならず司教の棄教さえ起こった。キュプリアヌス自身も身を隠して迫害から逃れた。迫害に対して殉教した者、棄教してローマの神に犠牲を捧げて証明書を得た者、偽の犠牲証明書により迫害から逃れた者があった。さらに問題となったのは迫害が収まった時に棄教した者が教会への復帰を望む事例が多数起きた事である。このような時代にキュプリアヌスは教会を中心とした信者の結束を高めることにより対処しようとした。キュプリアヌスは最終的には殉教するのであるが、迫害の時代に教区を棄てて逃亡したという負い目を抱えながら、ローマ教皇との政治的やりとりや信者のとりまとめ等々、殉教という危険と教会という組織運営という現代にもあるような俗事の間で奮闘する様子が切なくも文章から伝わってくる。
■ キュプリアヌスの背教者について(2011.2.6)
同じくキュプリアヌスの「カトリック教会の一致について」と対をなす教え。一旦背教しながら、また教会への復帰を望む人々に対する対応に教会内の分裂が生じている中、キュプリアヌスは信者に深い悔悟を求める立場に立つ。彼と対立する助祭フェリキッシムスが、背教者の教会復帰を簡単に認めることに、キュプリアヌスは大いに不快を示すのであるが、現実は彼の思い通りではないようだ。彼は信者に対して、「毎日浴場に行く者、贅沢な食事をとり、その食物を貧しい者に施さない者、髭を抜き髪を飾る男性、高価な飾り物を付けた衣装を身にまとう女性、髪の毛を染める者、黒い粉末で目の縁取りを描いたり、眉の線を描いたりする者、あなたが失ったのは自分の魂なのだ」と呼びかけるのであるが、呼びかけがあること自体、まさしくこのような信者が多いことを物語る。偽の犠牲証明書の流通や投獄されたキリスト者への差し入れが許されていたこと等を思うと、皇帝の「そう頑にならなくともローマの世俗を認めさえすればよいのだ」という呼びかけに、「いや私はキリスト者であるから偶像崇拝は絶対に拒否します」ということを公言する信者には、寛大なローマ人も法令に基づき処断せざるを得ないという状況が目に浮かぶようだ。神が絶対である以上、教えは世俗を超越してしまうのだ。
■ キュプリアヌスの死を免れないことについて(2011.2.16)
「中世思想原典集成」の解説には「この時期に流行病により斃れる人が増えたことに、不安を感じていたキリスト教徒に安心を与えるためにキュプリアヌスが記述した」云々とあるが、実際には、殉教の勧めであり、キリスト教徒はこの世を捨てたのであるから、早くキリストの許へ行こうと、信者に呼びかけるものものである。キュプリアヌス本人が殉教を避けて逃亡したという負い目がこれを書かせたのは明白であり、本人が殉教せざるを得ない状況に自らを追い込もうとする暗い情熱が透けて見えてくる、そんな論だ。自らの殉教が常に頭の中にあることが、筆を滑らせているのが解る。例えば、殉教とは神から与えられた恩寵であるので、必ずキリストの内に生まれ変わることができる、という主張に始まって、死は通過点であり、早く死を過ぎれば楽園が約束されており、既に死んだ知り合いがそこにもう住んでいる、という三位一体を背景とした最後の審判という考えに反するような主張に至っている。
■ 神の怒りに関する解釈(2011.4.21)
ギリシア人は神が怒るとは考えていなかったが、ユダヤにとって神が怒るというのは当然の考え方のようであり、この考えをキリスト教も引き継いで今に至っている。次項の「ラクタンティウスの神の怒りについて」マップに先立って、「中世思想原典集成」の解説を図にしてみた。
■ ラクタンティウスの神の怒りについて(2011.4.21)
ラクタンティウスは、怒りのないところには権力もない。しかし神は権力を有しており、それゆえに権力がそれに依って立つものである怒りをも有していなければならないと主張する。怒りと権力の関係については、地上の国家や政権は、畏怖によって守られていなげれば崩壊してしまう、誰か身分の低い者からでも、この感情を取り上げたならその者は万人の格好の餌食となる、ましてや、天上の王国の尊厳が怒りと畏怖なしに存立しうると考えるべきでない、と述べる。現代のキリスト教の教えでも、神の怒りがキリスト教の宗教としての厳格さを保つために必須だとしているので、基本的にはアウグスティヌスを経てラクタンティウスの説明が現在に引き継がれているのだと考えられる。もちろん矛盾はあるので、ラクタンティウスはギリシア・ローマの哲学者の言説に反論する形式を取ることにより、これを解消しようとしている。
■ アリウス主義者カンディドゥスのウィクトリヌスへの手紙(2011.5.28)
アリウスというのはアレイオスのことで、このあたりは日本語に訳する時に統一して欲しいのだがギリシア読みをするかラテン読みをするか、それぞれに事情があるのであろう。この論も長い間論争と教会の中の紛争の元となったアレイオス主義に対して、後に正統的立場とされる立場から述べられるアレイオス主義者に対する論駁である、これからも教義に関わる微妙な違いを持つ二者の間の論争については、現代に伝えられた正統とされた方の主張を分析することとなる。当然のように排除された方の主張は殆ど伝えられることがないので、客観的な分析のためには、一方的な主張の中から両者の違いを再現する必要がある故に、不明な点が残るのはやむをえない。
両者の違いは我々現代の視点からみると僅かである。僅かな違いしかないというのは、一方的な論駁であるのに、論駁にあたって新たな言葉、多くの場合ギリシア哲学の用語あるいはギリシア語そのものを持ち出して、定義が不十分なままにこの新しい言葉を中心とした議論の展開を行って、無理やりに自説の正さを主張するという態度からも明らかである。もし、両者に明確な違いがあるのなら、既に定義済みの言葉を使ってその違いを明らかにすることができる筈だからである。なじみのない外国語(ギリシア語)を持ち出すという時点で論者からみた彼我の違いが僅かであるということが分かる。ということは現代の我々にとって両者の違いは、論者の立場よりもはるかに切迫感がないともいえる。
この後も、父と子の関係について詳細かつ難解な議論が続く。
■ ローマ市の弁論家マリウス・ウィクトリヌスのアリウス主義者カンディドゥスへの手紙(2011.6.6)
元々マリウス・ウィクトリヌスはローマで新プラトン主義のラテン語への翻訳などをしていたと言われている。その後キリスト教に改宗し、ギリシア哲学を援用して三位一体などの教義概念の強化に努めた著作はアウグスティヌスに大きな影響を与えたことで知られている。
この論では、イエスは神の被造物であるとするアレイオス派を反駁する。在るもの(オン)と在らぬもの(メー・オン)との分類を縷々述べた後、神はプロオン(先なる在るもの)全体であるとして、在るもの(イエス・キリスト)は自分の父の内にある自らに固有な力によって、隠されていた在るもの(オン)それ自体が現れるという仕方で生成した。それゆえに、父と子は同時ではあるが、二つのものが同時なのではなくて、唯一のものであるとする。この生成、あるいは行いの現れとは、父の存在することが行いの原因であり、行うこと、すなわち子は、存在することそのものから生まれて来るのであり、結果としてイエスは神と同一本質(ホモウーシオス)である、と説く。
この同一本質(ホモウーシオス)なる言葉については後に、既に異端として断罪済みのサベリオス主義を思い起こさせるものとして問題となるのであるが、どちらにしても微妙な問題をプロティノスの新プラトン主義を下敷きに敷衍する、ウィクトリヌスの論には無理な点がある。マップにすると論全体は三つに大きく別れるのが分るのであるが、その三つの部分を結ぶ二つの結節点が弱いのだ。プロオンたる神とキリストの生成の結節、およびキリストの生成とホモウーシオスの結節、がそれだ。
■ ポワティエのヒラリウスの三位一体論 第二巻(2011.7.15)

Hilarius Pictaviensis
ポワティエはフランスの中西部、交通の要衝である。この頃、ローマ皇帝コンスタンティウス三世はアレイオス主義に傾き、皇帝の意向に沿う形で開かれたベジエ教会会議(356)において、ヒラリウス(315-367)は、反アレイオス主義の立場を貫いたために、小アジアのフリギアに追放される。その後、ヒラリウスは復帰するのであるが、フリギアにいる間に、アンキュラのバシレイオスから相似本質説(ホモイウシオス)を学び、サベリオス的なニカイア信条と相似本質説は和解が可能であると考えるに至り、西方教会において最初に三位一体論を著した。これはその長大な論の第二巻である。
ところで、ヒラリウスの論は過去のものであるかと言うとそうでもなくて、2007年10月10日のサンピエトロ広場における教皇ベネディクト十六世の一般謁見演説に、このヒラリウスが取り上げられていて、アレイオス派に反対して展開したヒラリウスの三位一体論が賞賛されているのだ。確かに異端は研究の対象であるかも知れないが、確固として異端であり、闘い続けるという姿勢は、未だに変わらないようだ。
ヒラリウスの論はギリシア哲学の流れをくむ東方教会とは明らかに違ってきていて、言(ロゴス)という論理を思い起こさせるギリシア語を使わずに、言(verbum)を用い、論の途中で言葉(sermo)と混用するなど、論を進めるのに論理ではなく、AであるからAなのだという、いささか強引な同義反復(トートロジー)を用いるなどして、神は人間には把握できるものではない、従って議論は不要であるという立場を強く押し出しているように思える。
さらにヒラリウスは三位一体の一つの位でありながら、今ひとつ分り難い聖霊についても説明し、これだけ言って分らない奴がいること自体がおかしい、等と言っているのだが、依然として聖霊が何か、筆者にはよく分らない。
■ ポワティエのヒラリウスの三位一体論 第三巻(2011.8.9)
第三巻は、生まれざる父、つまり最初を規定することができない存在である神と、その子が一体であるということを論証しようとするものだ。勿論、議論がアクロバティックなものとなるのは仕方がないので、ヒラリウスは、人間が不完全なものであり、所詮、完全な存在である神については知る事はできないのだ、というエクスキューズを用意しておいて、話を進める。ここでヒラリウスは栄光というキーワードを用いる。栄光:Gloriaはなかなか概念を掴み難い言葉であるが、神から発せられる眩い光という意味が拡大されて、絶対的な神の力を自らがいわば身体を張って証明することで、神の偉大さを表現する、というような意味を持つようになったと考えられる。ヒラリウスは父と子が位各として一体であることを示すために、子が父に栄光を与え、父は子に栄光を与えるという聖書からの引用を使う。また、父の内なる子、子の内なる神という説明によりこれを強化することを試みる。
ヒラリウスは、この困難な説明の末に、最終的に人間に神の業は理解することができないので、人間の知恵、そのものに意味がない、とまで言ってしまう。これは知的活動をキリスト教という文脈においては否定してもよい、という態度に繋がるものであるから、その後の西欧社会に、彼の考えがどのように受け継がれていっているのかは、これからも吟味すべき問題だろう。
■ アンブロシウスのエクサメロン(2011.10.29)
アンブロシウスはローマ帝国の高級官僚であった。ミラノの首席執行官であった時に、アレイオス派と反アレイオス派の調停に乗り出したところで、民衆の中に居た子供の「アンブロシウスをミラノ司教に!」という声をきっかけとした民衆の後押しを受けて、ミラノ司教となったといわれている人物だ(怪しい、やらせじゃないのか)。
この頃、ヴァレンティアヌス帝の弟であり、東方皇帝のヴァレンスがゴート族の反乱に手を焼いたり、ヴァレンティアヌス帝の長男であるグラティアヌスがヴァレンスの援軍として出かけたり、そのヴァレンスが反乱軍との戦いで戦死したり、その間にヴァレンティアヌス帝の二番目の皇后ユスティナが幼い息子を皇帝にしたり、グラティアヌスの任命で軍人のテオドシウスが皇帝になったりと、ローマは混乱と衰亡の時代であった。
その上、皇后ユスティナと東方皇帝ヴァレンスがアレイオス派擁護方で、グラティアヌスとテオドシウスが反アレイオス派であり混乱に輪をかけたような状況にあった。このような中で、反アレイオスであるアンブロシウスというのは、ユスティナを非難攻撃したり、最終的にテオドシウス帝を懺悔・屈服させた上、「皇帝は教会の中にあり、教会の上にはない」と宣言するなど、ローマが衰亡するのに対して、西方教会を世俗の権力の頂点に押し上げた人物である。
エクサメロンあるいはヘクサエメロンは創造の六日間のことである。アンブロシウスは創造のステップ毎にこれを解説するのであるが、論が錯綜してること、ギリシア哲学を軽視していること、時に抑制から外れた言を述べるなど、聖人というよりは姦智に長けた人物の文章のように見える。
■ ヒエロニュムス書簡集から書簡二十二 エウストキウムに宛てて(pdf size:1.1MB)(2011.12.12)

Eusebius Sophronius Hieronymus
ヒエロニュムスと言えば、ラテン教父のなかでは、その著作や標準ラテン語訳聖書、ウルガタ(editio Vulgata)の完成によって、アウグスティヌスと双璧をなす重要な人物とされている。ヒエロニュムスは、そのアウグスティヌスとも書簡の交換をしており、アンブロシウスとも親交があった。そればかりか、正統を継ぐ東方教会の重鎮であるナジアンゾスのグレゴリオスにコンスタンティノポリスで教えを受けたり、同じくニュッサのグレゴリオスの知遇を得たりして、その正統性をローマで疑う者は誰もいなかったことと思われる。
382年から三年程ローマに滞在し、ローマでは上流階級の夫人サークルで絶大な人気を得た。なかでも、寡婦のマルケラ、同じく寡婦のパウラを弟子とし、この書簡はそのパウラの三女であるエウストキウムに宛てたものである。正統キリスト教の教えを東方教会から受け継ぎ、当時の教皇ダマススの支援を受けているというのは、ローマ上流階級に受け入れられる必要条件を満たして有り余る。
必要条件は満たしていても、もちろん、上流階級夫人にモテるかどうかは別問題である。ヒエロニュムスは347年生まれだから、ローマに入った382年と言えば35歳前後か。自らキケロの徒と呼んでいた程の文学に親しんでいた上に、聖書の引用は自由自在。雅歌をちりばめて教えを説くことができる上に、上流階級の生活を斜にみて少し冷たく扱えば、モテない筈がない。二人の寡婦が夢中になるのも無理はなかろう。エウストキウムはヒエロニュムスの21歳程年下でその頃14才前後。ヒエロニュムスが書いているように、類い稀な美人だったらしい。
で、このエウストキウムに宛てた書簡なのだが、息苦しい程に処女を誉め讃えるものだ。ヒエロニュムスは結婚した女性より、処女が神の許でも上位にあるとまで言い切る。また、マリアがキリストを産んだ後も、ヨセフと夫婦生活は一切なくて永遠の処女である、という説を世間に認めさせてもいるのだ。なぜこうも処女にこだわるかと邪推すれば、この時、ヒエロニュムスはこの書簡中にも述べているように、既に去勢しているらしく、背後で渦巻くその暗いリビドーが、この息苦しさの原因と考えると合点がいく。実は、エウストキウムには4歳年上の長女プレシラがいて、一度結婚していたが離縁して戻ってきており、ヒエロニュムスは、上流階級の何不自由ない令嬢であるプレシラを、断食を伴う修行に追いやって死なせているのだ。当のエウストキウムは結局、処女のままヒエロニュムスの手元に置かれる事になって、彼女を伴ってヒエロニュムスはベツレヘムに至っている。
この書簡のマップを作りながら、訳文でありながらその息苦しさに、最後は少し端折った程だ。
■ アウグスティヌスの三位一体論第一五巻(pdf size:2.9MB)(2012.1.19〜)

Aurelius Augustinus Hipponensis
その一
アウグスティヌスの三位一体論第一五巻は彼の膨大な三位一体論のダイジェスト版ともいうべきものだ。アウグスティヌスの論は三位一体を強化するのではなくて、三位一体が絶対化された上でそこから何が導き出されるかを述べるものである。ただ読み進むうちに多くの点で違和感を感じた。キリスト教教義の上で、というものではなく、これまでのギリシア・ラテン教父の著述に流れるもの、それは数々の異端を排除しつつ、正統を確立しようとする数多くの教父達の思考の積み重ねから湧き出たものなのだが、その流れとアウグスティヌスの考え方には明らかに違いが見られるのだ。
アウグスティヌスが現代のキリスト教において聖人として崇敬されているように、もはやその評価は変えようもなく、筆者が違和感を感じた点について、訳者はアウグスティヌスによる日常を超越する宗教的言語使用である等と述べて、通常の議論を飛び越えている。例えば、アウグスティヌスは実体のもつ性質という一般的言語使用を超えて、性質について述べることは実体について述べることと同じと主張するのであるが、単一な本性にあってはなぜそう言えるのかは述べず、理解すべきと主張する等、確かに言語を「超越的」に使用している。もちろんキリスト教徒がアウグスティヌスの「超越的使用」を認めるのは、認めなければ聖人の言に矛盾が露呈してしまうからだ。
ただし、アウグスティヌスが北アフリカのヌミディアに生まれ、同じく北アフリカのヒッポレギウスで教父としての活動を行ったという事実の、当時のローマから考えても辺境における活動という地理的状況や、西暦410に起きた、西ゴート族アラリックI世によるローマ蹂躙という政治状況等を、アウグスティヌスの著述を理解する上で考慮に入れなければならないと思われる。すなわち、アウグスティヌスが新プラトン主義とキリスト教思想を統合した、あるいはアウグスティヌスに残る誤謬がプロテスタントに利用された、等の指摘は、アウグスティヌスが、東ローマ帝国に残るギリシア哲学を基礎とするキリスト教哲学とは遠く離れていたこと、有り体に言えば、北アフリカの辺境に居てキリスト教の主流からは外れていたことを勘案した上で吟味する必要があると思われるのだ。
例えば、彼は三位一体を記述する述語がその本性を表すことを強調した後、「これら三つのもの、記憶と理解の働きと慈しみ、または意志は、神である至高の不可変の本質存在にあっては、父と子と聖霊であるのではなく、父ひとりがこれら三つのものである」、あるいは「子は父から流れ出た記憶であり理解の働きであり慈しみである」と述べたり、聖霊についても、「聖霊は知恵から出た知恵であるので、聖霊ご自身がこれら三つのものをもつのであり、また聖霊がこれら三つのものをもつのは聖霊ご自身がこれら三つであるもの」で、「そのようなことが聖霊にあるのは、聖霊がそこから出たものから、そのことが聖霊に与えられることによって」と述べるなど、新プラトン主義の影響を受けていることは理解できるとしても、あたかも父が子より優位であるかのように、また聖霊が父から発出したもののように言うのは、正統的理解からは離れているのではないだろうかという疑いを筆者に持たせる。
また例えば、彼はパウロの言葉「私たちはいま鏡を通して謎のうちに見ています。しかし、その時には顔と顔を合わせて見るでしょう」や、「私たちは、顔の覆いを取り除かれて、鏡のうちに主の栄光を映しだしながら、栄光から栄光へと、主と同じ似姿へと変えられてゆくのです。それは主の霊の働きによることです」を根拠にして自らの考えを述べる。彼は、パウロが「栄光から栄光へ」(de gloria in gloriam)という言葉を付け加えたのは、たとえ不敬虔のうちにあっても、また悪徳が断罪に値するものであればあるだけ、いっそう確かにこの本性は誉め讃えられるに値する、と結論付けたり、またそれは「私たちが神の子であることの栄光」から、「神をあるがままに見ることによって、神と似たものになることの栄光」へと移りゆくということである、等と述べている。アウグスティヌスの論の前者は、不敬虔にあっても誉め讃えられるべき本性があるというのは、原罪はなく本性が不敬虔な状態にあるだけという解釈であるように見えるし、後者は、人間が神と(似たもの)に成り得るという大胆な解釈であり、三位一体を絶対化することによって、キリストの受肉による救済を無視しているのではないか、という疑問を呈さざるを得ない。どちらもここまでのキリスト教哲学の流れから言えば、異端と看做されても致し方ないのではないか、というのが筆者の感想である。
さらに、アウグスティヌスの議論は、彼自らの神秘体験「…そしてついに、一瞬の瞥見によって、存在するものに到達した。そのときわたしは、『あなたの見られないもの、すなわちあなたの永遠の能力と神性とは世界の創造以来造られたものを通じて明らかに認められる』のであるが、しかしそれを凝視することはできず、わたしの弱さのために、打ち退けられて平生の習慣に追いもどされ、いま一瞥したものに対するなつかしい思い出と、香りをかいただけで味わうことのできなかった食物に対するような物足りなさを感じるのみであった。」(告白、7-17)に基づいていると考えざるを得ないのだ。そこで、彼は述べる。「私たちはいま鏡を通して謎のうちに見ています。しかし、その時には顔と顔を合わせて見るでしょう」。
この記述の敷衍は、個人と神の関係を第一にすることで、キリスト教の母であるとされた教会の権威を、脅かすものと看做すことができることから、確かに正統からみたプロテスタントの誤謬に対する手助けの論であるとも言えるし、さらにアウグスティヌスは、上のパウロの言葉に含まれる「謎:エニグマ」についてこれを理解できないのはラテン語とギリシア語の修辞的な学問を知らない人々の言である、と述べ、ここから彼の現代の西洋哲学に流れ込むとされる持論を発展させるのだ。
しかしながら、いわゆる、『神の神秘な啓示は「謎」と呼ばれ深淵な意味をもつ(詩編49:4、78:2、エゼ17:2、ダニ8:23、ハバ2:6)が、ただ一人モーゼには「謎」によらず、直接的な啓示が与えられた(民数12:8)ー以上は新聖書大辞典、キリスト新聞社から引用ー』を考えると、パウロが神の似姿を謎のうちに見ていると述べたことについては、モーゼほど神に愛されていない我々には間接的にしか啓示が与えられていないのである、とパウロが言っているのだと理解した方が納得し得る。しかし、アウグスティヌスはそうではなくて、本論で、至福直観(人間として神と顔と顔とを合わせてみること)を自らの経験も交えながら強調していること、旧約の内容は彼の血肉となっているであろうことを考え合わせると、アウグスティヌスが「謎」から彼独特の論を導き出したのは、彼に何らかの意図、つまり、彼が回心の時の経験に始まる自らの考察を「自分のたずね求めていたものが掴みがたいものであることを見いだした時、何も見いださなかったと人が思わないため」と述べ、ここから「掴みがたい事柄の探求において前進することがあるかぎり、また、それほど大きな善をたずね求めることによって、いっそう善いものへと人が次第に作りかえられてゆくことがあるかぎり、探求を中止すべきではないから」と論を発展させて、モーゼの如き至福直観はモーゼにのみ限られるという従来の考えを否定して、至福直感は自らに現れ得るし、そうであるなら、全ての人間に現れ得ると考えたからではないのか。
アウグスティヌスの論はその時間空間的位置を考慮しつつ検討すると、正統と異端、運命に懸命に抗う東ローマと滅びゆく西ローマ、そして辺境の北アフリカにある彼、などなど、なかなかにスリリングであると言わざるを得ない。
その二(2012.2.16)
アウグスティヌスの三位一体論マップはこれまで筆者が作ってきたマップのうち最大規模のものになろうとしている。予想通り、アウグスティヌスがヨーロッパの思想の源流の一つであることへの確信と、その思想が異端ではないかという疑いと、読み進むうちにますます深まる疑惑により、より詳細に分析しなければという考えがそれをドライブしているからだ。
読み進むうちに彼が(聖人を彼なんて呼んで良いかどうか判断に苦しむが、異教徒の立場だから勝手にそう呼ぶことにした)、拠り所とする議論がほぼパウロの言葉、中でもコリント人への第一の手紙と第二の手紙、およびゼベダイの子ヨハネが記した蓋然性は極めて低いとされるヨハネの福音書より、さらに後に成立したと考えられているヨハネの手紙、であることが明らかになっていく。コリント人への手紙について言えば、パウロがイエスの言葉に如何に独特の解釈をしたかと言っても、イエスの記憶を濃く残す他の使徒が存命かあるいはそれに連なる人々がいる間は、その影響を無視できないと思われるのに対して、アウグスティヌスは、それを無視してパウロの言葉の都合の良い所を抜き出していると言わざるを得ない。また、ヨハネの手紙は当時の教会に生まれた混乱を収拾するために書かれたと考えられているのに対し、アウグスティヌスはその本意から外れて、これまたその一部を自らの都合のよいように抜き出して、牽強付会な引用を行っているのではないかという疑問が拭いきれない。また聖書全体からの引用が、例えばヒエロニュムスに比べて圧倒的に少ないことも特徴の一つである。
彼の文章を解析すると彼が非常に慎重な性格であることが分る。どういうことかと言えば、これまでに分析した教父の議論は、文章のフラグメントあるいは節(クローズ)が次々と直接的にあるいは短い距離で連結しているのに対し、彼の議論は非常に複雑なネットワークを作っているからだ。つまり直接的な読者の理解を得ようとしてはおらず、文章上遠く離れた位置にある節との関連を意識しなければその真意が理解できないようになっているのだ。なぜこのように複雑な構成になっているかと言えば、アウグスティヌスが頭脳明晰で議論の意味ネットワークを非常に大きなレベルで容易にハンドリングできる能力を持っているという可能性と、読み手から異端に係る異議を申し立てられないようにしている可能性の両方があるのではないかと考えられるからだ。
一方、彼自身がエクスキューズしているように、この議論が草稿段階で彼の手からそのコピーが持ち出されて公開されてしまったので、内容に不備がある、つまり議論の平仄が一致していない可能性もあるので、断定はできない。ただ例えば彼がアカデメイア派に対する反駁を述べている箇所、言葉とその元となる内的な知識について述べるところで、内的な知識は感覚器官によるのではないから確固としたものであるという前提を置いた上で、「見えるものと実際にあるものの間で違うところが多々あり、このため、真実らしく見えるそれらのものの仮象にすっかり群がり取り囲まれ、正気でないものが自分は正気だと思うほどである」、「このことからアカデミア派の哲学が力を揮った」とアカデメイア派の懐疑論に反駁するのであるが、その後で「私たちの身体の感覚だけではなく、他人の身体の感覚も、私たちの知識をはなはだしく増し加えているのだということを告白せねばならない」と述べるなど前後に矛盾があり、彼が哲学的議論については不慣れであると判断してもよいかどうか迷う、ひいては彼のエクスキューズが実は彼の異端の糾弾からの防波堤ではないかと疑うところだ。だが、彼がキケロの著作「アカデメイア派」に親しんだことも事実であるので、結局アカデメイア派の懐疑論の影響を受けているのではないかと疑わざるを得ない。
またロゴス・キリスト論と同時に人間の言葉に係る論を並列させて、彼の中心的議論である似姿と謎を通して神に近づく、という話を展開する場面で、「神から生まれたのではなく、神によって作られた神の似姿である人間の言葉である」(人間には神にも似た超越的なところがある)、「それは音声として発せられるものでも、また音声による類似像として私たちの内部に思考されるものでもない」(肉体以外のなにものかも我々の構成要素である)と、思わず議論を踏み外して、(人間が神的な観点からみて超越的実体と物質的・肉体的実体とに二元的に構成されているとする)グノーシス主義の影響を受けているマニ教の考え方(アウグスティヌスがかつて信じていた)が現れてしまった、と考えられる記述もあって、彼が異端と断じられても不思議はなかったと思われる。
しかし、彼が北アフリカのヒッポに暮らし、ゲルマン人の圧迫を受ける中でこの書を著したこと。その後、西方教会のなかでは彼の書がゲルマン人の中で愛読されたことを考えると、彼の異端性はローマ教会の評価を受ける前に信者の間に流布してしまったと考えるのが妥当であろう。となると、現代まで続く西欧のキリスト教哲学は、それまでのギリシア・ユダヤキリスト教哲学との断絶の後、アウグスティヌスの独自の考えがその源流となっているのではないかという疑問を打ち消すことができない。
その三(2012.3.17)
この三位一体論を読み進めていくうちに最も違和感を感じたのは、キリストが受肉して人間を救う道筋を人間に示したというそれまでの考えを、アウグスティヌスはどうもネガティブに捉えているようにみえるところだ。例えば、15節直前に「すなわちそれは『私たちが神の子であることの栄光』から、『神をあるがままに見ることによって、神と似たものになることの栄光』へと移りゆくということである」とあるが、これは人間が神と(似たもの)に成り得るという大胆な解釈であり、三一を絶対化することによって受肉による救済を無視しているのではないかと疑いをもたざるを得ないし、36節の最後に「そして、慈愛は神から出るものであり、私たちのうちにあって私たちが神のうちに留まり、神ご自身が私たちのうちに留まるように働くものであるとすれば」や「そしてこのことを私たちが認識するのは、神がご自分の霊を私たちに分け与えられたからであるとすれば」とあるのは、神はキリストの受肉を通じて人間に働きかけたという考えから逸脱しているのではないかと思われるし、キリストこそが人間の傍らに居たことを軽視しているのではないかとも思われる。つまり、あまりにも三位一体を教条的に捉えるゆえに、アウグスティヌスは、神とキリストの本質の同一(ホモウーシオス)を述べるだけでなく、位格(ヒュポスタシス)をも同一のものと見ているのではないかと筆者は疑ってしまうのだ。
予定説つまり、人間が最後の審判において救済されるのか救済されないのかは、神のうちに予め決定されているという考え、の芽生えがアウグスティヌスの論に見られるのも気になるところだ。例えば、14節に「不敬虔のうちにあっても、悪徳が断罪に値するものであればあるだけ、いっそう確かにこの本性は誉め讃えられるに値する」という言葉があって、これは不敬虔にあっても誉め讃えられるべき本性があるというのは、原罪はなく本性が不敬虔な状態にあるだけという解釈をとることができる。また、32節に「 何ものもこの神の賜物に勝るものはない。これだけが永遠の国の子供たちと永遠の滅びの子供たちとを分つ」という言葉があって、これも聖霊が分け与えられているかどうかで、審判の結果が決定済みということで予定説につながっていくのではないかと考えられる。
こうしてアウグスティヌスの教条的な三位一体の捉えは、聖霊が人間に分け与えられるなら神自体も人間に分け与えられる筈という考えにつながり、従って人間は教会を通じることなしに、個人的に神とつながることができるとするプロテスタントに発展することは容易に想像できるし、予定説はカルヴァン主義につながって後年の米国の宗教的な礎となるのであるから、まさしく、アウグスティヌスは現代キリスト教の始まりであるし、ひいては西欧社会の哲学的な始まりであると言ってもおかしくはないであろう。これが歴史にどのような結果をもたらしたかについては、種々の考え方があろうが、筆者としては辺境の地で育まれたアウグスティヌスの考えが、ローマの衰亡とゲルマン民族の進出という歴史的偶然から、後世にかくも巨大な影響を与えたという事実を知って、偶然が導いた人類の歴史発展ということに深い感慨を持つ事を禁じ得ないのだ。その後の血塗られた歴史を思うと、アウグスティヌスの存在意義もしくはその哲学の批判的再解釈は、現代において決して無駄なものではないと筆者は考える。
その四(2012.3.29)
長い長いアウグスティヌスの三位一体論のマップは一応の完成をみた。読み進むうちに、アウグスティヌスが置いていた地政的状況がもう少し明らかになってきた。それはカルタゴ教会会議の存在である。カルタゴ教会会議はアウグスティヌスの活躍の前後にカルタゴで開催されていたアフリカの司教による一連の会議の総称である。アウグスティヌスはもちろん中心的存在で、いわばこの会議がアウグスティヌスの応援団の様相を呈している。この時期、西ローマ帝国はゲルマンの部族に蹂躙されて風前の灯火であり、ローマ教会だけがゲルマン部族がアレイオス派ながらもキリスト教徒であることに助けられて、存在を保っていたのであるが、このカルタゴ教会はローマ教会の方針にも異議を唱えたり、原罪と自由意志に対する理解の未成熟なブリタニア出身の、ペラギウスの一派を異端とするようにローマ教皇に迫ったりして、一定の力を持っていたのだ。カルタゴ教会がアウグスティヌスを守るのに巧妙なところは、このペラギウスの論を反駁すると同時に、必ずしもペラギウス派擁護側とは言えない、西方にエジプトに始まる修道制を持ち込んだヨハネス・カッシアヌスに、半ペラギウス派というレッテルを貼って異端となったペラギウスと同列の扱いをしたことだ。
カッシアヌスはエジプトの修道制を持ち込んだことからも分るように、東方教会のキリスト教哲学に馴染んでいるから、アウグスティヌスの論に様々な従来のキリスト教哲学に馴染まない点を見いだし、これを指摘していたものと思われる。例えば、ニュッサのグレゴリオス教理大講話とアウグスティヌスの論を比べると、それまでのキリスト教哲学からみてアウグスティヌスの論はいかにも受け容れ難い。カルタゴ教会が東方教会と哲学的に議論を交わすのではなく、レッテル貼りやローマ教皇に対して圧力をかけることで、アウグスティヌスを守ろうとしたのではないかという疑いが晴れないのだ。そう考えると、アウグスティヌスはなかなかのやり手かな、という気がして、彼の三位一体論を額面通りに受け取ってよいものかどうか、迷う。
■ アクイタニアのプロスペルのルフィヌスへの手紙(2012.4.7)
タイトルが分り難いが、アクイタニア出身のプロスペルという名の人物が、友人であるルフィヌスへ出した手紙という形式をとる教説である。プロスペルはアウグスティヌスの心酔者で、アウグスティヌスを論難するヨハヌス・カッシアヌスに反駁するために、まず原罪が人間の本質を汚すまでには至っていないので人間は必ずしも神の救いを必要としないという分りやすい異端者であるペラギウスを論敵とし、ペラギウスの考え方には批判的であったカッシアヌスを半ペラギウスと呼んで、論駁するという、いささか複雑な状況を作り出してまでアウグスティヌスを守ろうとするカルタゴのキリスト教徒の代弁者である。論の進め方からも、その立場上からもこのプロスペルという人物がアウグスティヌスに匹敵するとは考えられない、彼の心酔者であるから。逆に心酔者である故に、アウグスティヌスの考え方が最も純粋に彼に表れていると看做すこともできるわけで、確かに彼の論からアウグスティヌスの最も伝えたかったことが見えて来る。
そしてプロスペルの論から、アウグスティヌスが予定論の創出者であり、神の恩寵と慈愛を強調する一方で、それまでのギリシア教父の教えであるキリストの受肉とこれによる人間の普遍的な救済を無視していることが明らかとなる。また、人間の原罪が世代交代を通じて伝達されるとしたりして、確かにプロテスタントの原型を提示していることも理解される。その予定論は単に最後の審判の後の永遠の生命への召しが、予め神により決定されているとするに留まらず、例えば異邦人については、予定の段階があって、一段目にまず、異邦人が福音に触れるかどうか、二段目に、福音を聞いた異邦人が信仰に入るかどうか、三段目に他のキリスト者と同じく永遠の生命に向かって召しがあるかどうかの全ての段階において、神の予定に沿って人間が動くとしている。
従って、人間が善に向かうか悪に向かうかは、人間の弱い意志の在り方によるというそれまでの考えが否定されて、破滅へと向かう自由意志はあると言えるが、回心した自由意志には結果が神に帰するという理解の賜物が与えられたので完全性は持たない、という理解が与えられて、これも世界は神により予定されているとする考えからの帰結であることが分る。また、最後の審判においては、誰も功績に関わりなく滅ぼされない、誰も功績に応じて自由にされるのでないとして、救われるのか、救われないのかは、人間の認識の能力を超えて分らないとする。一方、それを不安に思う必要がないのは、「すべての善き人々は、神の恩恵が彼らにその賜物を授けることによって天の国に入ることであろうことや、また、いかなる悪しき人々も、彼らの邪な性質がそれに値しないことによって、天の国に入ることはないであろうということは明らかだからである」と極めて雑駁な説明をするのみである。アウグスティヌスは、自らは、神の顔を見る寸前までいったと認識しているので、自分の天国行きは確実と考えているのは分るが、その他大勢つまり、アウグスティヌスの考えが広まって現在に至るまで、特にプロテスタントの諸派の信者は相当に悩むことであろう。
またプロスペルは、異邦人に対する福音について、「教会の幕屋が広げられないような、世界のある国、地方があるとあえて言う人は誰もいないと私は思う」と述べたり。「私に求めよ、私はもろもろの国を嗣業(割り与えられた土地)としてお前に与え、地の果てまでもお前の所有として与える」という聖書の言葉を引いたりして、キリスト教布教において副次的に他国の支配があり得ることを述べたりするが、彼がアウグスティヌスの言に忠実であるとすれば、アウグスティヌスに、キリスト教世界特にプロテスタンティズム世界とその周辺および全世界の、この後惹起し現在まで続く惨禍に係る責任はないとは言えないのではないか、とも思う。
■ ネストリオスのアレクサンドレイアのキュリロスへの第二の手紙(2012.4.24-29)

Nestorius
その一
ネストリオス(ギリシア読み)はエフェソス公会議で異端とされ、終にはエジプトの上ナイルの砂漠に追放されてHibis (al-Khargah)で客死するが、その教義を信ずるネストリウス(ラテン読み)派が東方に形成され、終には中国にまで至ることになった。この書簡はネストリウスの教説を非難するキュリロスに宛てたものである。この時期、キュリロスはネストリウス弾劾の準備を着々と進めていたのであったが、ネストリウスの対キュリロス観はのんびりとしたもので、この書簡もキュリロスを教え諭すような論調である。自分がキュリロスによって終には追放されようとは露ほども思っていないことが解る。 この両者にそれほど深刻な教義の違いがあるのか思うのであるが、当事者にとっては重大なことであったのだろう。両者の間がなぜこれほどこじれてしまったのかというと、ネストリオスがアンティオケイア学派で在るのに対し、キュリロスがアレクサンドレイア学派に属して、両学派の争いがその原因であると説明されている。しかしながら、ネストリオスはコンスタンティノポリスの司教であり、時の東ローマ皇帝テオドシウスII世に司教を叙階されているのであって、同じ皇帝がエフェソス公会議のネストリオスの断罪の後、その著書の焚書を命じていたりして、寛大なるべきローマ皇帝としてその勅命はあまりにちぐはくであり、つまりネストリオスの追放に関しては相当な裏工作のあったことが推測される。つまり、キュリロスにはもっと個人的な恨みのようなものもあるような気がする。
ネストリオスに対するキュリロスのネガティブ・キャンペーンは、ネストリオスはマリアをキリストコス(キリストの母)と呼ぶべきと主張するような冒涜の者である、というものなのだが、ではキュリロスの主張はと言えば、マリアはテオトコス(神の母)であるというものである。ネストリオスとしてはマリアが神の母であるとするのは神に対するマリアの優先を暗示することになるし、アントローポトコス(人間の母)と呼ぶのはキリストの受肉の奇跡をおとしめることになるので、マリアをキリストコスと呼ぶべきという、まっとうな主張をしているように思えるのであるが、そこまで考えの至らない一般民衆に、キリストは神であるからマリアはテオトコスと呼ぶべきとしつこく言い張るするキュロリスの話は、より浸透しやすかったのだろうと思われる。
エフェソス公会議においてネストリオスが断罪されたのも、公会議にネストリオスの出席する前にキュリロス一派が一方的に異端を宣言したり、そういう筋書きとなるようにネストリオスが会議に遅れるようなキュロリスの工作の結果である。しかしその後、ネストリオスの友人でアンティオケイアのヨアンネスが公会議に五日遅れで到着し、今度はキュリロスの弾劾・破門宣言を出したり、これに慌てたテオドシウスII世が、ネストリオスとキュリロス両者を監禁したり、キュリロスが素早くこれに対処して監禁を解かれたのに、ネストリオスがエジプトに追放されたり、その後にヨアンネスがキュリロスと和解の合同文書を出したり、エフェソス公会議の二十年後に開かれたカルケドン公会議で、キュリロスが属するアレクサンドレイア学派の主張するキリスト単性説ではなくネストリオスの属したアンティオケイア学派の主張するキリスト両性説が宣言(カルケドン信条)されたり、そのまた三十年後にカルケドン信条とキリスト単性説の調停を図る統一令が皇帝ゼノンから出されたり、その統一令に反発してシリア、パレスチナ、エジプトにおいて単性説を信条とする分離教会が形成されたりで、この論争の主座は二転三転する。
そもそもアレクサンドレイア学派の云う単性説(Monophysitismus)とは、「人間の本質をなす精神と肉体がそれぞれの独自性を失うことなく合一して一つの全体となっているように、キリストはロゴスと肉から一つの統一された現実的生命となったのであり、肉を支配する活力はロゴスに由来する」とするもので、キリストに人間の霊魂があるかどうかについては否定的である。それゆえ人間としての霊魂がキリストにないとすると、単性説によればロゴスの受肉による人間の霊魂の救済がなくなるのではないかという疑いが生まれる。結局、アンティオケイア学派の云うように、キリスト両性説、すなわち、キリストは「真に神であり、理性的魂と肉体からなる真の人間である」という判断が最終的に示されるのであるが、それはさらに後の時代になってからである。しかしネストリウスの名誉回復がなされることは終になかった。
筆者はネストリオスを信奉する者ではないが、キュリロスの叔父であるアレキサンドレイアの司教テオフィロスが、アイスキュロス・ソフォクレス・エウリピデスの自筆原稿まであったとされるアレクサンドレイアの大図書館を破壊したり、キュリロスに直接の責任はないとはされているものの、キュリロス派がアレクサンドレイアの哲学者にしてアストロラーベの発明者とも言われているヒュパティアを虐殺してアレクサンドレイアから哲学者を逃散させ、アレクサンドレイアの地の文化的終焉を招いた事を決して心良くは思わない。
その二(2012.4.29)
このネストリオスのキュリロスへの書簡に対して、キュリロスからネストリオス宛の書簡もあり、両者の間に何通かの手紙の交換がある。両者の書簡を読んだ感想を予め述べておくと、キュリロスなる人物はいかにも下衆で哲学的な素養も低いことがわかる。その代わりに極めて政治的に動くことのできる人間であることは、その書簡のもってまわった言い回しや、ネストリオスのような温厚だが世間知らずの人間を手玉に取るような仕掛けが書簡に施されていることからよくわかる。
最終的にはキュリロスの単性説は否定される、というよりは両性説と混ぜ合わされてしまうのであるが、キュリロス派は異端とされることなく、ネストリオウス派は異端となったままという、政治的にはキュリロスの勝利に終わる。つまり、キュリロスとネストリウスの争いを総括すれば、言い張るものが終には権力を得て、温厚かつ論理の通った主張をなす者が衰亡し、大分に時間の経った後で言い張るものの害が明らかになるという、この世の在り方をよく示す事例である。以下のような、キュリロスの政治的戦術は現代にも十分通じると思われるので、参考になるのではないか。
- ■ 筋が通らなくても単純なメッセージを大衆に示すこと 〜 キリストは神なんだからマリアは「神の母」であると言い張る
- ■ 大衆を動員して教養あるマイノリティを攻撃し大衆に自信を持たせること 〜 アレキサンドレイアにおいてユダヤ教徒を迫害し哲学者を惨殺させる
- ■ 遠隔の地にある事情をよく知らないオーソリティを活用すること 〜 同輩であったローマ教皇ケレスティヌスにネストリオスを弾劾する手紙を送り賛成意見を得る
- ■ 事情をよく知らない無能な為政者にオーソリティの意見だと吹き込むこと 〜 時の東ローマ皇帝テオドシウスII世にネストリオス弾劾を承認させる
- ■ オーソライズされた会議を開催させること 〜 テオドシウスII世にエフェソス公会議を招集させ同時にネストリウスが出席できないように恫喝を含むあらゆる手段をとる
- ■ オーソライズされた会議で相手を一方的に弾劾すること 〜 エフェソス公会議においてネストリウスの出席のないままに一方的にネストリウスの異端を宣言する
- ■ 問題が生じた場合には迎合する大衆のいる地元に帰ること 〜 素早く監禁から脱出し地元に帰還するときには凱旋の演出を行う
- ■ 敵対者の息の根を完全に止めること 〜 群集を送り込んでテオドシウスII世の宮殿を包囲し圧力をかけてネストリウスをエジプトに追放させる
■ キュリロスの第四書簡ーネストリオスへの第二の手紙(2012.5.13)

Cyril of Alexandria
注意して読まないとその違いが明らかとならないのだが両者の違いはこの先にあって、ネストリオスが「死について言及しようとするときには、それによって神である言(ロゴス)が苦しみうるものであるとは思われないように、単一のプロソーポン*2における苦しみうる本質(ウーシア)と苦しみえない本質を表示するものとして『キリスト』という名称を掲げているのである」と述べて、キリストの人間性を重視したのに対し、キュリロスは「神の言(ロゴス)が、ご自分の本性(フユシス)において苦しみを受けられたのではない。実に神性は苦しみを受けることはない。この方ご自身の肉体が苦しみを受けたので、この方ご自身が私どものためにそれらの苦しみを受けられたと言われる」と述べるのである。
つまり、キュリロスはキリストに神性と人間性の両方が並立しているのを認めず、「言(ロゴス)は、一個別者(ヒュポスタシス)として、名状しがたく把握しがたい方法で、理性的な魂に生かされた肉を自分に合一させて、人間となられた」とする。この合一(ヘノーシス)が何であるかは名状しがたいと言うのである。であるから、合一したとすると必然的に合一前の二つの本性は違うことになる。これをキュリロスは「真の合一(ヘノーシス)となるような結合された本性(フユシス)はそれぞれ異なるものではあるが、双方から成るひとりのキリスト、ひとりの子がおられるのである」と言う。
問題を複雑にしているのは、この頃、本質(ウーシオス)と位格(ヒュポスタシス)、そのラテン表現である、フユシスとペルソナの定義が定まっておらず、教父によってその意味するところが違うところである。その他にも自説を正当化するために新たなギリシア語を取り込んだりするものだから、話が錯綜してしまっている。例えばキュリロスの云う合一(ヘノーシス)はその後殆ど使われないし、ネストリオスの云うプロソーポンもアレキサンドレイアでは殆ど使われなかったといわれているから*3、二人の論争の間、互いの言葉の意味と主張が相手に正確に伝わっていたかどうかは怪しいところである。
ただし、キュリロスの言う「真の合一となるような結合された本性はそれぞれ異なるもの」が位格ではなく本質(ウーシオス)であるとすると神の唯一性が問われてしまうので、キュリロスが云う本性(フユシス*4)とは位格(ヒュポスタシス)でなければならない。さらに結合された本性、というのが位格の結合であるとすれば、本質(ウーシオス)において等しいものが、位格(ヒュポスタシス)においても結合されてしまい、結果としてキュロリスは神とキリストが同一のものであると言っていることとなり、これは時代を遡って既に異端とされていたサベリオス主義の天父受苦説を再び説くことになるのではないか。サベリオス主義が弾劾されたのは、キリストの人間性を無視しキリストが受肉によって人間となって人類を救済するという点がないがしろにされている、とされたためである。キュリロスの説を読むといかにもこのサベリオス主義に近いのではないかと疑わざるを得ない。一般的には、キュリロスには、後のコンスタンティノポリス公会議(381)に弾劾されることとなる、ラオディケイアのアポリナリオスの単性説「キリストはロゴスと肉から一つの統一された現実的生命となった。肉を支配する活力はロゴスに由来する」の考えが流れこんでいるとされており、サベリオス主義まで遡ることはないようだ。実際には、キュリロスの単性説は後に否定されて、キリストには神性と人間性の両方が内在するという両性説が採用されることになるのである。ただし、キュリロスは断罪されないまま、アレクサンドレイア派は残ることとなる。
筆者がキュリロスに疑いの眼を向けているのは、本質(ウーシオス)と位格(ヒュポスタシス)の意味を意図的にすり替えて使っていたのなら、極めて政治的な発言であると言わざるを得ないし、キュリロスが本当にギリシア哲学者のそれまでの議論を理解していなかったとすれば、迂闊と言わざるを得ない。筆者はキュリロスの自説を声高に言い張る様子から、キュリロスは実は政治的な人間で、かつ哲学にも疎いのではないかと疑うのである。
キリストの両性説は、キリスト教発展の初期からギリシア哲学者とユダヤの教師により形成された、極めて微妙なバランスの上にある議論と筆者は考えるのであるが、ローマ教会がキュリロスを異端とせず、逆にネストリオスを断罪したという点に、この時代、ローマ教会には教説による判断に加えて、既に教区の大きさや影響力、教区の信徒の数などへの考慮が働き始めていたのではないかと考える所以である。
- *1 ロゴス(言)はイエス・キリストのことである
- *2 ここにおけるプロソーポンは「ヒュポスタシスの表れ」、「具体的な存在の外的な表れ」を意味するという(本文の注)
- *3 キリスト教神学辞典, 教文館による
- *4 フユシス(自然本性)は、キュリロス(370-444)に先行するニュッサのグレゴリオス(335-394)が「教理大講話」の中で言及している
■ キュリロスの第一七書簡ーネストリオスへの第三の手紙(2012.6.10)
この手紙はキュリロスがローマ教皇のケレスティヌスに手を回して、ネストリオスへの弾劾をオーソライズした後のもので、余裕たっぷりにネストリオスに最後通牒を伝えるという内容である。原典集成の訳注にもあるように、「キュリロスにおいては、フユシス、ヒュポスタシス、プロソーポンは同義語であり、具体的な個別者である」とされているのであるが、訳文においては、適宜辻褄が合うように、これらが区別して訳されていることに注意しなければならない。つまり、キュリロスは異端とされずネストリオスが異端のままであるので、現代のキリスト者からはキュリロスに対する肩入れがあるのだ。
この手紙は、聖書に基づいてネストリオスを弾劾する部分と、キュリロス信条ともいうべき部分、すなわちエフェソス公会議をネストリオス弾劾の場として、キュリロスの下書きをエフェソス信条として宣言しようと目論む部分から構成されている。つまりエフェソス公会議の全体シナリオとなっているのだ。ただしエフェソス公会議が完全にキュリロスの思惑通りになったわけではなくて、アンティオケイア学派のヨアンネス・クリュソストモスが、キュリロスを逆弾劾したり、同じくアンティオケイア学派のキュロスのテオドレトスがキュリロスに反対する論を執筆したりしたので、キュリロス信条がエフェソス信条として宣言されることはなかった。
このキュリロス信条ともいうべきものは「××は排斥される」という十二条からなるネストリオスに対する通告で、ローマ教皇のケレスティヌスの同意を得たゆえか、いかにも居丈高な書きぶりである。しかし、その内容と言えば、フユシス、ヒュポスタシス、プロソーポンがごっちゃに用いられ、その他にヘノーシス(合一)やらインマニエル(われらと共におられる神:「おのおのの若い女が生む子ら」というユダヤ教的解釈も可能)などの言葉が恣意的に使われるなど、それまでの三位一体説に係る哲学的経緯を理解した上の論ではないと言わざるを得ない。またキリストは単性であるから自分達は正しくて、追放を目論むネストリオスには「貴殿の場合は、書面で聴従の意を表明され、宣誓のうえ、貴殿の汚らわしく神を冒涜する教説を排斥し、私ども一同、すなわち、東西の司教たち、教師たち、信徒の指導者だちが考えていることを貴殿も考え、教える旨表明されなければならない」という言葉を突きつけるなど、その品性も高いとは言い難い。
この後もアレキサンドレイア派の暗躍は続いて、単性説を唱えるエウティケスを立てたエフェソス教会会議が、東ローマ皇帝テオドシウスII世により招集され(449年)、アレキサンドレイアの司教ディオスコロスが会議の議長を務めて、ローマ教皇レオ I世の名代として出席したコンスタンティノポリス総主教のフラウィアノスを追放したり、前出のキュロスのテオドレトスを罷免・追放したりして、後に教皇レオ I世をしてこの会議を「エフェソス強盗会議」と呼ばしむる程であった。
最終的にエウティケスはコンスタンティノポリス教会会議(448年)において断罪され、単性説はカルケドン公会議(451)で否定されて、キリスト両性説すなわち「キリストは真に神であり、理性的魂と肉体からなる真の人間である」が宣言されるのであるが、その後もアレキサンドレイア派は勢力を保ち続ける。東ローマ皇帝ゼノンがキリスト単性説とカルケドン信条との調停を図る統一令を宣布(482)する等してもこれに反発し、単性説勢力の強いシリア、パレスチナ、エジプトにおいては分離教会が形成されることとなった。ただし、これらの分離教会は後に「非カルケドン派」を名乗ることとなって、カルケドン宣言に反対しているわけではないとして、キリスト教の正統からは離れていないことを自ら主張している。
■ 偽マカリオスの大書簡(pdf size:1.6MB)(2012.11.1)
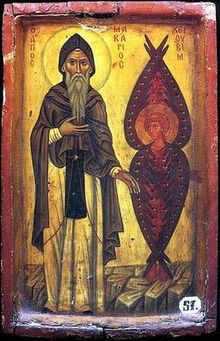
St. Macarius the Great standing next to a Cherub
偽マカリオス(Phseudo-Makarios)文書とはエジプトのマカリオスが著したと伝承されてきたが実はメソポタミアのシメオンの著作であると考えられる文書を云うのであるが、なぜマカリオスを称したかと問えば、異端とされたメッサリア派がこの文書を引用するところ大であったため、過去の聖人であるマカリオスの名を冠してこの文書が焚書されるのを避けたのであると推定されるのだという。メッサリア派がなぜ380年頃のアンティオケイア教会会議で断罪され異端とされたかと云えば、彼らは人間の霊魂には悪魔が存在していてそれは洗礼を通じても追い出されず、祈りと禁欲生活を通してのみ、聖霊が霊魂に入ると主張したためで、そうなると洗礼を否定することとなるし、神が創造された人間の霊魂に何時悪魔が存在するようになったのかという問題が起きるからでもある。
この長々しい偽マカリオス文書をマッピングしていくと、どうも同一人物が著述したのではないのではないか、あるいは同一人物でも書いた時期が大分に違うのではないかという疑いを持たざるをえない。章立てとは別にどうも途中でニュアンスが違っているように思えるのだ。
最初の部分、第一章から第二章の11節までは、は、メッサリア派の主張と言われる、魂が悪魔に支配されているという話ではなくて、単に人間の魂の成長の必要性が強調されており、むしろ偽マカリオスは自由な選択意志(プロアイレシス)が人間に与えられていること、それは人間が新たな霊的誕生のために、多大な忍耐をともなう戦いや競技・競争を経験するためのものであること等を主張しているに過ぎない。ただし、「人間の側からの恊働と努力なしに、神の力と恩恵によるだけで人が前へ前へと成長し続けていくことはできない」と述べるなど、神の恩恵に加えて人間の側の努力が必要であることを強調するので、受肉による人類の救いの完全性に疑問をなげかけるものではないのか、という疑いが残る。
十二節からは、やや唐突に愛の話が現れるが、第一の部分を強化している部分と思われる。これが第五章の最後まで続く。第六章は修道院における振る舞いについて述べるのであるが、修道者をひたすら神に祈る者と祈る者を支える者の二つに分けて、それぞれの在り方を述べるのであるが、祈る者を第一とするいわば祈り至上主義とも取られかねない。
第十二章から始まる結論では、メッサリア派が非難される原因となる、祈りによって聖霊が顕現するということを述べるばかりか、「確かにわれわれが示してきたように、完全に自らの自由意志にもとづいて戦いを続けていくならば、聖霊が共に顕在し、混合されることによって、われわれは神の子、王の子、キリストの兄弟となり、限りなく永遠にキリストと共に王として君臨するであろう」などと言い始めて、面食らうのであるが、見方を変えてユダヤ教徒がキリスト者として振る舞っているというふうに考えると、これらの記述が納得できる。マップを遡るとそこかしこにユダヤ的な考えの表明があって、筆者は逆にこの論からユダヤ教の考え方を知るようになった程だ。つまりメッサリア派の主張という見方もあるのかも知れないが、この論を当時のユダヤ教徒からのキリスト教へのアプローチと考えることはできないだろうかということだ。
■ ディオニュシオス・アレオパギテスの天上位階論(pdf size:1.5MB)(2013.2.19)

Pseudo-Dionysius the Areopagite
偽ディオニュシオス文書として名高いこの論は、アレイオス・パゴスの議員であるディオニュシオスが著したものとされてきた。アレイオス・パゴスとはアレイオスすなわち、アレス(ローマ神話では軍神マルス)に捧げられたパゴス(丘)という意味で、この丘に置かれた古代アテナイの最高法院を指すものである。ここからアレオパギテスとは、最高法院議員のことを指すのだと云う。ディオニュシオス・アレオパギテスは使徒言行録にその名が述べられている(使17:34)。つまり、彼はアテナイで布教したパウロによって入信したギリシア人であり、パウロの直弟子となった実在の人物と考えられる。が、しかし、ディオニュシオス・アレオパギテスはその後、偉大な神学者ヒエロテオスに師事し、その教えを伝えようと著作を著したとされることとなった。すなわち彼は使徒時代の最初の教父とみなされることとなり、その著作には特別の敬意を払われることとなった。その著作群がディオニュシオス文書あるいはアレオパギテス文書と呼ばれて「聖書に次ぐ権威」さえ持つことになったのだという。
ところが近世の研究によってディオニュシオス文書は使徒時代ではなく、紀元500年頃に書かれたものであることが証明され、これらの文書の著者は偽ディオニュシオスと呼ばれるようになったのだと。ディオニュシオス文書は6世紀前半から東方キリスト教世界に流布しだしたが、証聖者マクシモス(Maximos Homologetes:580-662)により文書の真作性が確信されると、東方キリスト教世界で高い権威を有することとなったという。西方世界ではこともあろうにフランク王国のヒルドゥイヌス(Hilduinus:855-861)が、教会政治的思惑からディオニュシオス・アレオパギテスと、パリの初代司教として殉教したディオニュシオス(フランス語でDenis、聖ドニ(Saint-Denis)と呼ばれた)とを同一人物だとする説をたてたというので、余計に話が混迷する。この頃はカロリング・ルネサンスの時代であり知識人の間でギリシア文化に対する関心が高く、聖ドニとディオニュシオス・アレオパギテスの同一視(エラスムス(Erasmus:1466-1536)の時代まで続く)と相俟ってディオニュシオス文書が注目を浴びることとなったのだと。文書は9世紀にエリウゲナ(Eriugena:801-877)によってラテン語訳が行われるとともに、西方キリスト教世界でも東方と同様に絶大な権威をもって受容されていくことになったのだと。その真作性が疑われるようになったのはルネサンスと宗教改革の時代以降のことであるとされているのだと。
ここまでが解説からの引用であるが、いや周到に準備されたというか偶然が偶然を呼んだというのか、あるいはギリシア哲学者の執念の結晶というのか、この論の現代までの影響の度合い、というよりはキリスト教に無関係だったものがその後に完全に血肉となってキリスト教に組み込まれてしまっている、という状況を考えると実に感慨深いものがある。
偽ディオニュシオス文書の成立した500年頃という時期は、カルケドン公会議(451)も終わってオドアケルが西ローマ帝国にとどめを刺したり(476)、東ローマ皇帝ゼノンが単性説とカルケドン信条との調停を図る統一令(ヘノティコン)を宣布したり(482)、ユスティニアヌス1世がにアテネのネオプラトニック大学を事実上閉鎖したり(529)の起きた時期と重なる。キリスト神学に造詣が深いと言われたユスティニアヌス1世が弾圧した新プラトン学派の考えの記述された著述が、聖書に次ぐ権威を持つようになるというのも、実に興味深い。
だが、本文第三節の「われわれの知性は現れている美しさを隠れている美しさの写しと捉え、感覚で捉えることのできる芳香を知性で捉えることのできる発散の象徴と捉え、物質的な光を非物質的な光の賜物の似姿と捉え、聖なる悟性的思考の訓練を知性による観想の充満と捉え、この世のもろもろの配列の秩序を神に属する事柄にふさわしい調和のある整えられた状態と捉え、聖なる聖体に与ることをイエスに与ることと捉えたりする」と書かれた部分の太字部分などは、それまでのキリスト教父の教えとは全く異なると言ってよいだろうから、この書は教父の教えと云うよりは新プラトン主義(もちろんその当時は主義というようなカテゴライズはされていなくて、師弟関係あるいは先人の論を引き継ぐという状況を後代の人がそう呼んだに過ぎないのだが)の解説、あるいはこの書が書かれた時期の新プラトン主義者の、非物体的な知性である天使群が天上で位階を形成している、というヘブライズムの新プラトン主義の立場からの説明として読むべきではないのだろうか。
ただし新プラトン主義の立場から言えば、浄化・照明・完成という上昇のありかたが否定神学とともに語られるべきであるのに、この天上位階論ではどちらかと言えば、神の周りの第一の位階のセラフィム、ケルビム、王座について、第二の位階の主権、力、能力(天使)について、そして第三の位階の権勢(権天使)、大天使、天使については語られるのであるが、神への還帰である浄化・照明・完成については無造作に扱われている感じがする。その代わりに、神性が如何に位階を通じて下位に分有という形で伝達されていくかについて詳しく語られている。この、分有がイデアの完全なるコピーであるという考え方がアリストテレスにより否定された後に、イデアは不完全なるコピーすなわち分有という形式で下位に伝えられ、それゆえに位階が形成されているという論については、分り易いとは言い難い。
そこで、この論においてはイデアのコピーや分有ではなく、位階を如何にビジュアルに表現するかということに力点が置かれているようで、天上の位階、すなわち第一の階級にあるセラフィム(熾天使)、ケルビム(智天使)、王座(座天使)、第二の階級にある能力(能天使)、主権(主天使)、力(力天使)そして第三の階級にある天使、大天使、権勢(権天使)がどのように形象表現されているかについて詳しく語られる。そのせいで、この後天上位階論は、ヨーロッパにおけるそれ以降の天使のイメージの基礎となったとされているから、確かに偽書でありながらキリスト教に深く組み込まれることとなったという歴史的事実はもう打ち消す事ができないのだ。
ともかくも、またキリスト教がかくも妥協を重ねつつもその本質を失わなかったという点が見事であると思う。
■ ディオニュシオス・アレオパギテスの神秘神学(pdf size:1.6MB)(2013.2.27)
「神秘神学:Περί μυστικής θεολογίας」と題された論は、浄化、照明、完成という上昇のトリアスの中でその最後の段階である完成、すなわち天上の位階から神性の根源への上昇の段階について論じているものである。神性の領域は人間の知性の範疇では捉えられないから、人間の言語の限界を常に考えつつこれを語る、否定神学の方法がとられるのである。神は「超存在」(ὑπερούσιος)と呼ばれるが、既に否定神学を超えた範囲にあるゆえにあえて神秘神学に属する用語として用いられる。「超存在」とは神があらゆる存在と非存在を超えていることを示し、われわれの知識によっては捉えることが不可能であるゆえに、われわれは神を知り得ないということを知る「無知」(ἀγνωσία)を得る。神が「神秘なる観想対象」と呼ばれるとしても、それは神を「観想」(θεωρία)することができるのではなく、できないのでもないということ、つまり「無知」によって知られることを表しているのだと。別の言い方をすれば「無知」とは神の「闇」に入ることである。この「闇」は光の不在や欠如ではなく、光と闇を超えたものえある。偽ディオニュシオスはこれを「光の過剰」であると言うと。
われわれが「無知」によって「超存在」を知るためには、われわれは自分自身の知の限界を超えなければならない。神が知られえないということをわれわれが知るためには、われわれは自分自身の知るという働きそのものを超えなければならない。その超越が「超脱」(έκστασις)であるという。「エクスタシス」とは、自分の「外に」(έκ)「立つこと」(στασις)あるいは自分を「超えて」新しい自分が「立てられること」であると。それは自分の存在を超えた新しい存在、自分の知を超えた新しい知、自分の生を超えた新しい生である。そのような新しい次元での在り方は自分のあり方を超えている限りではもはや「自分の」あり方ではないが、しかし、そのあり方はほかのもののあり方ではないのだから、自分のあり方ではないような自分のあり方であると。
「超脱」は自分のあり方の次元そのものを更新することであるが、それは自分の力で行うことができない。それが可能になるのは、神の「愛」(έρως)によるのだと。「神の愛は超脱的であって、愛されたものが自分自身に属していることを許さず、自分の愛する相手に属するようにさせる」(神名論)と言われていると。この神の愛は被造物に対して発出するとともに、被造物を還帰させる愛であると。モーゼは神の闇に入るや神と合一(ἕνωσις)したと。神の愛によってわれわれは神との合一に至り、ここが神秘神学の終局であると。
以上はディオニュシオスの神秘神学論に対する解説の言うところであるが、語れないものを語るためにエクスタシスが必要でこれは神の愛のみによってもたらされるというのであるから、不完全性理論の示すように、論が不完全であることを知ることは可能であるが、不完全を超えることについて記述する論は不完全な論の内から発することはできないから、矛盾しているのであるが、それを言っても仕方がない。
どちらかと言えば、この論は神から出発して下降に伴う付与を実体とする肯定神学と神に向かって上昇する過程の除去を実体とする否定神学について説明したものと捉えた方がよいのではないかと思われる。少なくとも肯定神学は否定神学の反対の概念であると定義するのみで、肯定神学そのものを説明する資料が少ないので、あるいはこの論が肯定・否定神学の源流である可能性もあり、無視できないのだ。日本語の資料も少なくて、例えば、「キリスト教神学用語辞典」には、肯定神学を「cataphatic theology、神の自己啓示に基づいて神を積極的に論じる神学の形態、否定神学の反対」と説明してあるが、否定神学も「apophatic theology、有限な人間の能力の枠内では、神を概念化できないとする考え」(同書)のように説明される程度であって、探求を続けるべきであると思う。
肯定神学について「それは、あらゆる付与を超えているものを付与するには、そのものにいっそうよく類似しているものから仮定的に肯定を付与することが必要であり」、否定神学について「あらゆる除去を超えているものを除去するには、そのものからいっそう遠ざかっているものから除去することが必要だからである」とアレオパギテスは述べるのであるが、その結果として「万物の完全で一なる原因はあらゆる付与を超えているのであり、あらゆるものから絶対的に隔絶して一切のものの彼方にあるものの卓越性はあらゆる除去を超えているのだから、それ(神)には付与も除去もまったくない」と、正・反・合の原形がここに示されているのだと考えることもできる。
否定神学とこれと対をなす肯定神学に係るディオニュシオス・アレオパギテスの論は中世のトマス・アクイナスの思想にも流れ込むのであることを考えると、ここから哲学への流れと信仰への流れが分流しているのではないかという仮定が成り立つのではないか。そうすればさらにそこから二つの仮定を立てることができて、一つは、明らかな異端の教えが正統に組み込まれることによって哲学の分野における前述の正・反・合の原形の提示がキリスト教的正統性の裏付けをもつこととなったのではないかと、二つ目として信仰面から考えると、明らかに異端の教えがいつの間にか体系に組み込まれていった結果、その矛盾から涌き出す緊張感のゆえに、キリストの人間性についての想いと検証の道が繰り返し辿られることになったのではないかと。そう考えると、既に述べたパウロが持ち込んだ矛盾と本論の新プラトン派が持ち込んだ矛盾がもたらす不安定さこそが、絶え間の無い信仰の見直しとなって、信仰の命脈を保つ力の一つになったのではないかとも思われるのである。
■ ヨアンネス・クリマクスの楽園の梯子(pdf size:1.3MB)(2013.4.28)

神へと上る梯子
「楽園の梯子」というタイトルからは当然の如く、アーサー・C・クラークの「楽園の泉」が想起される。彼は自らを「汎神論者」としているようだが、「楽園の泉」の主題は宇宙エレベーターであるから、このSF作品のタイトルを決めるにあたって彼が「楽園の梯子」を意識していないと言う事は難しいのではないか。天空にある若き仲間を救うために独りエレベーターの索を上昇するというのも、両者の一致が偶然であるとする見方に組しないとして良いのではないか。
さて、ヨアンネス・クリマクスは7世紀のギリシャ教父で、シナイの聖カタリナ修道院の院長を務め、シナイ派のヘシュカズムの代表的人物とみなされている。ヘシュカズムとは静寂(ヘーシュキア:ἡσυχία)を基本として、絶えざる祈りをもって神との一致を目指す霊性の体系、のことであり、これには「神との積極的な交わりである祈りの生活には、内面的な静寂さを自発的に保つ」ことが必要だと考えるためである。
この論では、ヘーシュキアを実践する修道者は独住者(隠棲者)でなければならないとしているのであるが、ヨアンネス・クリマクス自身は独住生活者、半独住生活者、そして院長も務めたように共住生活者の三つを経験し、この論は院長時代に書かれたとされている。
と、ここまでが解説である。さて、ヘーシュキアには、冷静な理性(ヌース)、浄められた思考(エンノイア)が必要であると述べられるが、同時に「霊魂のヘーシュキアは、思慮(ロギスモス)を知ることであり」とされていて、「祈りの中間の段階は、言われたこと、考えられることの中にだけ思惟(デイアノイア)があることである」、「彼が賢く俊敏であるなら、その場の記憶からあらゆる咎め、怒り、心配、妨げ、苦難、飽き、誘惑、思慮(ロギスモス)を避けることができる」、「消失とは、無益な思索(フロンテイス)に囚われることである」、「思索(フロンテイス)を投げ捨てなさい。思考(エンノイア)を剥ぎ取りなさい。身体を拒絶しなさい」とあるように、彼の文脈においては「ロギスモス(思慮)」とは「乱雑な思い」という程度のもので排除すべきものであり、その後に「フロンティス(無益な思索)」から離れ、終には「エンノイア(思考)」からも脱して、「ヌース(理性)」だけが残るヘーシュキアに至る、ということのようだ。
なおかつ、今は地にあるヘシュカストは天上の天使と比較されて、天使は遂にはセラフィムに追いつき、地のヘシュカストは「幸いなるかな希望する者。三重にも幸いなるかな、来るべき 将来天使になるに違いない者」と表されている。
このとき、不受動心(ὰπάθεια:アパテイア)が理性を神聖にし、質料から引き離すために不受動心が必要であるとクリマクスは説く。「変わることなく主に願おう。というのも、情念の下にあるすべてのものは、情念に囚われた状態から不受動心へと進むからである」と、ヘーシュキアに至るにはアパテイアが必要であると言うのであるが、アパティアはギリシア哲学者の用法では、何事にも動揺することのない賢者の持つ優れた特徴であり、その後のギリシア教父達は「神の恩恵に助けられ て、人間もアパテイアの心境に達することができ、しかも完全な人間になるためには、それに達しなければならないと説いた」(新カト)とされている。だが、完全なる不動心は静寂であると看做すこともできるので、両者の違いが明確であるとは言い難いのではないか。
さてヘーシュキアは冷静なヌースが至る静寂であるが、一転して、ヨアンネス・クリマクスは「アガペー(神の愛)」について熱く語る。 この論で気になるのは、愛、についてἕρωςとὰγάπηの使い分けである。ディオニシオス・アレオパギテスの論では神の愛をἕρωςと呼んでいるのであるが、ヨアンネス・クリマクスは神の人間に対する愛をὰγάπηと呼び、人間同士の愛をἕρωςと呼んでいるようだ。ただし、神の愛を説明するために「人間的なものから、憧れ、恐怖、熱望、嫉妬、隷属、神への愛(エロース)譬えを与えることは悪しきことではない」、「幸いなるかな、熱狂的な恋人が自分の恋人に対して抱いていいるように、神に対して愛(エロース)をもつ人」と述べられているように、人間同士の愛を否定しているわけではない。
その他に、「主を愛する人(アガパオー)は、まず自分の兄弟を愛する」、「そしてあなたはあなたの愛する者たち(エラステース)を無敵にする」とあるので、神の愛が「アガペー」でその愛により愛される人間たちが「エラステース(単数形がエラオー)」であり、神の愛に応えて神を愛する人が「アガパオー」であり、神への愛を人間の愛に譬えて「エロース」と呼ぶ場合もあり得る、と考えられているようだ。
■ 証聖者マクシモスの愛についての四〇〇の断章(pdf size:1.2MB)(2013.7.26)

Icon of St. Maximus
マクシモスが如何なる発言によりキリストの両性を証したかについては、新カトリック大事典の解説「すなわち、両性が完全であるならば、キリストのうちに神的意志と人間的意志の二つの意思が存在しなければならない。しかし両者とも厳密には本性的意志であり、おのおのの本性の善性に適合する意志である。しかし選択的意志は本性に属さず、ヒュポスタシスすなわち個別存在に属す。そこで、キリストには本性が二つあっても、ヒュポスタシスはロゴス一つしかないので、選択的意志はただロゴスのみによって決定づけられる。このロゴスは神的意志の力により人間的意志を支配しているため、キリストのうちにある人間的意志は神的意志に一致しているのである」が解り易いと思われる。ただし、この事典のマクシモスの項は、「証聖者マクシモスの愛についての四〇〇の断章」も参照しているので、この訳者と事典の筆者の理解である可能性もある。
本書の解説によれば、マクシモスはコンスタンティノープルの有力な家系に生まれた。皇帝ヘラクレオスの戴冠に伴って筆頭秘書官に任ぜられるも三年後には職を辞してコンスタンティノポリス近郊クリュソポリスの修道院に入る。しかし626年のペルシアによるコンスタンティノポリス包囲に際してカルタゴに逃れた。その後、ローマに至り教皇マルティヌス1世の招集したラテラノ教会会議に出席して、単意説弾劾の決議文書作成に係る。しかし、イスラム勢力下の東方教会を支援しつなぎとめるため、キリスト単意説に関する論争を禁止(651)したコンスタンス2世により、教皇マルティヌス1世とともに逮捕され、マクシモスはトラキアに追放された。追放後も活動を続けたため再び逮捕されて舌と右手を切断されたうえ、黒海沿岸のラジカに追放されその地で没したという。
本編は証聖者の名の由来であるキリストの両性の証明ではなく、修道者に与える言葉として、伝えられてきた師父の言葉に依って神の愛について語るものであるので、その時々に読まれるべきものなのであろう。実際にマップにしてもそれぞれの断片的な言葉の間により上のレベルとのつながりを見出すことはできなかった。
なお、訳文中に「苦業」という理解に戸惑う単語が使われていたり、「倫理的行為」という単語が唐突に出現して、なぜethics (倫理学)という近代の概念の単語が使われて、ラテン語にいうPhilosophia moralis( 道徳哲学と訳される『新カト』)が、使われないのか等、訳者の意図が不明な部分が散見される。
■ ダマスコスのヨアンネスの知識の泉(pdf size:3.2MB)(2014.2.3, Friday)
Iohannes Damascenus
解説によれば、この書は哲学と異端史すなわち教会史・教理史を踏まえた上で神学に進むという構成を以て、現代に至るまでの神学教育の過程を規定するものになっているのだという。本説は三部構成が取られており、その陳述は過去の教父の教えを総合したもので、ヨアンネス自らの私見は入っていないと述べられている。またも解説によればその第一部「哲学的な章」はアリストレテレス・ポルフュリオス(232-305)の「アリストテレス・カテゴリー論入門(エイサゴーケー)とその注解であるアンモニオス(445-517)の「ポルフュリオス・エイサゴーケー注解」、およびアタナシオス(295-373)とシナイのアナスタシオス(-700)に依拠している。
同じく解説によれば、第二部「異端論」はサラミスのエピファニオス(315-403)の「パナリオン(薬箱)」の要約であり、また同じく、第三部「正統信仰の解明」はオリゲネス(185-254)の「諸原理について」、エルサレムのキュリロス(315-387)、エルサレムのヨアンネス(356-417)の「秘義教話」、ニュッサのグレゴリオス(335-394)の「教理大講話」、キュロスのテオドレトス(393-466)の「異端略史」などの流れにそった体系的な既述であるとされる。
さて、ヨアンネスは650年頃、ダマスコスで裕福なアラブ人キリスト者の家庭に生まれたと云う。ここでなぜ、生まれに言及するかと言えば、ヨアンネスの三位一体論をマッピングしていくと、既述は確かにキリストの両性論を述べているのであるが、どうもアレクサンドレイアのキュリロスの云う単性論に近い考え方を持っているように読み取れるからである。
彼は訳出されていない第一部「哲学的な章」においてウーシアについて説明するにも関わらず、第三部においてウーシアを「実在するもの」ではなく、ある存在の実在に関する考察を飛び越えて、実在するものの性質をウーシアとして取り扱うようになるからである。ウーシアに対する彼の説明からは、ヨアンネスがウーシアを実在に対する考察なしに、実在の性質をウーシアと考えているように見受けられる。これは訳者が『ヨアンネスの説明を踏まえて、ウーシアを「本体」、フュシスを「本性」…エンヒュポスタトンを「実在するもの」と訳出することにする』と説明しているところを見ると訳者もそう考えているのではないか。
例えばヨアンネスは、「二つの本性の本質的な相違は維持され続けるとわれわれは定義する。実に、創造されたものは創造されたものであり続け、創造されざるものは創造されざるものであり続けたのであり、…実に、一方は不思議な御業によって照り輝き、他方は侮辱に屈したのである」と、キリストの人間性が、打ち負かされたことになってしまったり、「栄光の主と、本性的に真に人の子である方…他方によって自ら苦しみを耐え忍んだとはいえ、不思議な御業も受難も同じこの方のものであるとわれわれは認めるのである」と、受苦がネガティブに捉えられていたり、「キリストの二つの本性はそれぞれ相違している、すなわち…キリストは両極端に結びついていると、われわれは言うのである」と、神性と人間性のアンバランスを強調したり、「この方の本性は、結合された唯一の実体を有するものとして、実体によって結び合わされているのであり、この点で父と霊と、母とわれわれと相違しているのである」、あるいは「実に、この方は『神と人間との双方に』類似したひとりの方であって」と、キリストが人間でもなく神でもない「実体」であってそれは神性と人間性が結合されて新たな状態にあると述べるのである。
これらに通底しているのは、ウーシアの本来の意味である「実在」の一致ではなく、キリストにおいて、性質としての神性と人間性が「合一」により結合あるいは合成されて別の「実体」になると云う考えなのであるが、それは、合成された新たな状態ということを仮定することによって、結局、キリストの「神性」と「人間性」の両方を否定していることになるのではないか、と思うのである。
さらには、「精神に主導される魂と粗雑な肉体である人間」が「精神が仲立ち」となって「神」と合成され、しかも精神は「神の譲歩によって」その「能力を発揮」する、あるいは「精神(ヌース)は、一個別者として自分に合一した神性の座となったのである」などと述べて、キリストの肉体を否定するような記述が続いて、ヨアンネスは、最後の晩餐においてキリストが使徒に与えた血と肉をないがしろにしているのではないかという疑問が湧くのである。復活についても「さらにわれわれの本性は、死者のなかから呼び起こされ、引き上げられ、父の右の座に着かされたとわれわれは言うが、個体としての人々の全体が呼び起こされ、父の右の座に着いたと言うのではなく、本性全体が個別者としてのキリストにおいて、そのようにされたと言うのである」などと述べて、キリストの肉体を伴った人間性すなわち、キリストにおける個別者としての人間性を無視して、キリストにおける人間性を人類全体の人間性と読み替えることによって復活をキリストの奇跡ではなく、人類の人間性の必然としているのではないか、とも考えられるのである。
また、キリストが神性と人間性という「本体」の結合であるとすれば、結合すべき両者の間には対応すべき重みが必要であろう。それゆえに神性は父から来た聖なるものであるから、人間性をもたらした母もこれに対応する聖なるものであるべきである。従って母を単なるキリストコス(キリストの母)ではなくて、テオトコス(神の母)であるべきという主張も、それなりに納得すべきなのかも知れない。だが、そう考えることによって、ここでもキリストの人間性が聖なる母に由来することになって、キリスト自身のものであるという観点が失われてしまうのではないか。
これらを考え合わせると、ヨアンネスには何らかの意図があって、即ち両性論を云いながらニカイア公会議で否定された単性論を持ち込もうとしているのか、あるいはアラブ人に特有な考え方があるとした場合、その考え方がされた結果、ウーシアを「自ら『実在』するもの」という概念としてより深いレベルで考えるのではなく、より上位概念である具体的な「本体」を重視しているのではないだろうか、という疑念が湧いたからである。私が彼の生まれにまで言及した所以である。
同時にヨアンネスの記述から、ヨアンネスが、神に祝福されたキュリロスと呼んで傾倒するキュリロスの考え方とは、ウーシアを人間性と神性の「存在」ではなく、それらの「性質」と捉えることによって、結局はキリストの人間性を否定することとなって、異端として否定されたアレイオス主義に通じているのではと、私は疑うのである。
もっとも、これらは、ヨアンネスがキュリロスに近いのではないかという私の疑いと、ヨアンネスの「だが、聖なる処女をキリストコスとはわれわれは呼ばない。なぜなら、その父サタンとともに寸断されてしまったが、汚らわしく、破廉恥で、ユダヤ人の心をもったネストリオスが、テオトコスと呼ぶのを拒否し、ただ一人すべての被造物に優って崇敬するに値するテオトコスを侮辱するために侮蔑の言葉として案出した恥辱の器だからである」という大人げない記述や、「この方を神を担う者と言ったり考えたりするという事態がわれわれに生じないように。受肉した神と。実に、御言ご自身が肉となり、処女によって受胎し、受け取った後、神として出て来られたが…」(第56章(3-12)聖なる処女は神の母(テオトコス)であること)と、その昔に否定された天父受苦説と紛うようなことを書いてしまう、という「怒りに我を忘れるとつい本音が出てしまう」という見方が、必ずしも的を射ていないのかも知れないし、あるいは現代のキリスト教徒の考えと私の疑いが異なるという所以かもしれない。
だが、第六二章(三(18))「意志と自由意志、精神、そして知識と知恵について」に至って、ついにヨアンネスは、自らが単性論者であることを暴露してしまう。キリストの受肉に係る神と対比した場合の人間の弱さを記述することに筆が滑ったか、「したがってキリストは本性的に人間として、また神として双方の意志を有しているが、人間としての意志は自分の見解に動かされることなく、その神的な意志が意志したことを意志して、御言の意志に従い、服したのである」はまだ良いとして、「本性的に自己に固有のことで苦しみを受けたのは、神的な意志の許諾によることである。死を免れるよう懇願したとき、その神的な意志の意向と許諾の下に、本性的に、死を免れることを懇願し、苦闘し、恐れたのである」とまで書いて、キリストが自分の教えが未だ弟子達に十分には伝わっていないうちに人間としての活動を終えることを悲しんだことを、まるで、死を恐れる小心者のように描いたことを考えると、結局のところ両性論を口では唱えるが内心は単性論者そのものであるのではないか、さらには、彼にはギリシア、ローマのキリスト者の剛胆さが全く伝わっていないのではないか、と考えざるを得ないのだ。
このようなキリストに対する態度や、矛盾する記述にみられるような論理の軽視が、何に由来するものなのか非常に疑問に思う。神を強く崇拝するが故に人間自身を、真理や死を恐れる小心者と捉えたり、同じく神を絶対視するゆえにギリシア・ローマの哲学的背景をキリスト教に見ることをしない態度は、さらに時代を下って、遂にはイスラムに通じると考えられるのではないか。
しかしヨアンネスはキュリロスの後裔であるとともに、ある意味正直な信仰者であることも事実であり、例えば第七七章(四(4))「なにゆえに,父でもなく霊でもなく、子が人間となったのか、また人間となって何を成し遂げたのか」において自分の信仰を吐露している部分は胸を打つものがある。
■ ストゥディオスのテオドロスの聖画像破壊論者への第一の駁論(2014.2.12)
偶像崇拝であるとする非難に反論することは、必ずしも容易ではない。イスラムが偶像を崇拝しないことを誇りにしているように、そこにはある程度の真実が含まれているからと考えられるからである。かつて私が聞いた、「祖母が仏壇に向かって手を合わせる様子をみて、その孫が『おばあちゃんは偶像崇拝者だ』と非難し、その祖母が嘆き悲しんだ」という話はこれを象徴的に表すものとして私の記憶に残っている。勿論、自分の信ずる宗教の純粋性を言い立て、かつ相手が旧く雑駁にして不純な宗教であるとして非難することにより、自分の優位を確認するという行為であるのだが。
さて、コンスタンティノープル近郊のストゥディオス修道院の院長でもあったテオドロスの偶像破壊論者への反駁である。テオドロスの偶像破壊論者への反駁は、唯一、破壊論者も崇拝する十字架を例にとって、十字架もまた模像物であるが、十字架という名前を共有しているが故に十字架を通してキリストを讃えているのである。それと同様にキリストの肖像もまたキリストと呼ぶという、名前の共有の故に聖画像を崇拝しそれを通してキリストを讃えていると述べるのである。しかしこの論法では、破壊論者が聖書には十字架についての記述はあるが聖画像についての記述はないゆえに画像を破壊すべきである、という主張に対しては十分な反駁とはなり得ないのではないか。
確かに十字架についての聖書の記述はあるが十字架の模造品についての記述はない、つまり画像への崇拝がこれを通して本性に対する称賛となり得るという聖書の記述はないので、画像破壊論者への反駁としては弱いのだ。さらにイスラムが聖典以外に物質的な崇拝対象を持たない(黒い石を除けば)ようにキリスト教徒が十字架を持たないことにでもなれば、偶像破壊論者への反駁はますます困難となろう。
その他、聖書に「あなたはいかなる像も造ってはならない。…私は主、あなたの神」(出20:4)という記述があるのも、話を面倒にしている。画像破壊論者がこれを根拠にすると、同じく聖書に、神がモーセに対して「あなたは炎の蛇を造り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば、命を得る」(民21:8)と言ったにしても、画像破壊論者を納得させるのは難しいのではないか。
ただ、本論の解説者の示すように、テオドロスの云う「両本性の結合のゆえに、彼の神性は身体的輪郭づけの下にありなからも、崇拝されまた栄光を帰されている」という両性論のもとに、「肉体が触れられ、掴まれ、見られるものであってみれば、ほかにどのような仕方がありうるだろうか。、別の仕方では、結合に由来する輪郭づけられない本性という異質の固有性を受け取ることはできないのではなかろうか」とあるように、その信仰告白を通じることによってのみ、神を知ることができるゆえの聖画像である、という点だけを強調した方が良かったのではないか。もちろん、この論が効果を発揮するのは両性論を認める者に対してだけであるので、これを認めない者達が偶像破壊論者となることはある意味仕方のないことと言わざるを得ない。
さらにテオドロスは「神性は受け取る側の本性の許容力に従って表現される」、しかして聖画像の内の神性は「相対的な分有によっている。こうしてこれらのものも恵みと栄誉に与るのである」と述べていることを考えると、彼の言をネオプラトニズム的に拡張すれば、相対的な分有とは理解力というロゴスの分有であると主張できるのかも知れない。つまり理解とは何かのキリスト教的解釈まで考察が及んでいて、興味深い。
■ 新神学者シメオンの一〇〇の実践的・神学的主要則(2014.2.26)

Simeón el Nuevo Teólogo
949-1022
訳注において、「東方教会の霊性の伝統に根ざす、『個々のキリスト者の内に三位一体なる神が内在する』という考えはシメオンの強い経験的確信である」と述べられるが、これが東方教会の伝統であるという根拠はまだ理解できない。私の理解ではアウグスティヌスに始まる神の内在という考えの方が西方教会の伝統としてあるのではないかと思うのである。
それはそれとして、東方教会において「神学者」と呼ばれる思想家は、福音書記者である聖ヨハネ、ナジアンゾスのグレゴリオス、そして「新神学者」シメオンであると云う。シメオンは949-1022を生きたとされていて、グレゴリオスは4世紀の人であるから、10世紀になれば「新」と呼ばれるのも納得できる。小アジアの地方貴族の家に生まれ帝国の官吏であった叔父の導きでコンスタンティノポリス宮廷で教育されたのだという。シメオンは、ストゥディオスの修道院に入ったがゆえにストゥディオスのシメオンとも呼ばれるとされる(新カトによる)が、実際には修道院では反発を受けて入って数ヶ月足らずで追放され、近隣の聖ママス修道院に入ったのだと。しかし直ぐにこの修道院で叙階されてここの修道院長になったのだから、ママスのシメオンでも良いのではないかと思われる。
東方教会では三本の指に入る神学者であるのに、西方教会では殆ど知られていないようだが、自己の神秘体験である「光の体験」を基に、「ニュッサのグレゴリオスやナジアンゾスのグレゴリオスのように、否定神学の伝統に立って、理性的知よりも、聖霊が謙遜で清い心に注ぐ、至福直感の恵みを通して語った」とされている(新カト)ので、まさしくアウグスティヌスに近い考えの人ではないかと思われるのである。
彼もまた信仰に燃える人であって、「『招命のとき(解説による)』この世から逃れると宣言した自分(シメオン)に対して身内や友人が止めたのは、悪霊の仕業である、その証拠に身内がシメオンの眼前で涙し悲嘆にくれ、それでもシメオンの気持ちが変わらないのを見て、身内が突然シメオンに対する怒りと憎しみで沸き立ったからである」と述べるのは、修道生活に入った後の言葉であるとは云え、直情径行な青年であるとしか言いようがない。修道士仲間と軋轢を起こしてストゥディオス修道院から追い出されてしまうのも仕方があるまい。
極端なのは身内に対してだけではなくて、シメオンの後見人であり、そもそもストゥディオス修道院に入るための口添えをしてもらった敬虔者シメオンに対する態度も相当なものである。彼、霊的父(敬虔者シメオン)を敬うあまり、「(30) 次のような者は明らかな信仰を示している。それは、導き手である霊的父が占めている場所をも聖なるものとして尊び、父の足元の塵を手で懸命に拾って、それを自分の頭にかけ、自分のパトス(情念)の癒しと罪からの浄めとして心に塗る者である…」と謙ってみせるという、尋常ではない態度を取るのである。
で、このような極端ともいうべき行動の末、霊的父に対する崇拝と、神の光を見たという自分の経験をないまぜにして、自説を説く内に、キリストに対する崇拝と霊的父に対する崇拝がシメオンのなかで同一視されてキリストを霊的父と同じレベルであると看做した上、自分が神の光を見たという確信をベースに、次第に自分がキリストと同じレベルではないかと妄想するようになったのではないかと思わざるを得ない。それは例えば、「(53)私たちの主なるイエス・キリストの、人にして神である「天に属する方の似姿」を、感知され意識される仕方で理性的・知性的自己にまとうことをしない者は、いまだ血と肉にすぎないものである」、という記述と、「(54)そのように見聞きして感知する者は、これらの言葉の意味がわかる。なぜなら、その者はすでに『天に属する方の似姿になっている』からであり」、などと述べているからである。
アウグスティヌスもそうであったが、自ら神の光を見たという確信を持ってしまうと、キリストよりも神に目が向いてしまいその結果、「キリスト教」が「神教」に変化してしまうという過程を目の当たりにしているような気がする。だが、この論の最後に「涙のうちにあなたの目から覆いが払われて、『いまだ一人も見たことのない方』(ヨハ1:18)をみるのである。そしてその方の愛(ἔρως)にあなたの魂は苛まれて、涙とともなる哀歌を歌い終えるのである。そのときには私のことを思い起こし、この卑しい者のために祈ってほしい。なぜなら、あなたは神との一致(συνάφεια)に、そして神との恥入ることのない心おきなさ(παρρησία)に到達したからである」という締めくくりを読むと思わず惹き込まれるから、確かにカリスマ性のある人物であることが分る。
■ ミカエル・プセロスの哲学小論集 (2014.3.10)
プセロス(1018-1081?)はビザンティン時代屈指の博識家として知られ、コンスタンティノポリスでミカエル4世の治世に官職に就いたのだという。コンスタンティノス9世の下で「最高の哲学者(ὕπατος τῶν φιλοσόφωῶν)」の称号を与えられ、多岐にわたる著作を残したという。学術的な著書は、古代の作品の要約の域を出ないものの、結果として特に哲学、思想の分野において新プラトン主義の復興、ひいてはその西方への伝播に重要な役割を果たしたのだ、ということが解説に述べられている。「プラトンの語るイデアについて」、「思惟的美について」はそれぞれプロティノスの「エネアデス」V9とV8の要約であるとされている。
マッピングしてみると、それぞれのボックスの繋がりがよく分らない。彼は最後に「以上がプラトン的イデアについての考察である。それはプラトンが多くの言葉を費やして詳細に語ったものを、私があなたのために簡潔に、より明瞭にまとめたものである」と述べるのだが、どうもこのプセロスの小論というのはプセロスがプロティノスを読んで作ったメモのようだ。つまり、何を言っているのかよく分らない。これはどうしてもプロティノスの著作を読まねばならない。ネオ・プラトニズムについてはこれまでにマッピングした著作群に頻繁に表れるのであるが、その体系についてはどうもはっきりとした理解が得られなかったので、丁度よいタイミングである。
■ ボエティウスの三位一体論(2012.11.8)
ボエティウス(Boethius)は教父ではない。東ゴート族の王テオドリックに仕えた、元ローマ貴族の家系に生まれた者である。王の信任を得て執政官にまで昇りつめたが、東ローマ帝国による西ローマ奪回を危惧するテオドリック王その人の命により終には処刑されてしまう。
この時代は、西ローマ帝国を滅ぼした傭兵隊長オドアケルを討伐してテオドリックが東ゴート王国を成立させ(493)、東ローマ帝国においては、カルケドン信条とキリスト単性説との調停を図る皇帝の統一令の草稿を書いたコンスタンティノポリス総主教のアカキオスが、このためにローマ教皇フェリクス3世から破門されて、東方教会と西方教会が分裂状態(484-519)となり、テオドリック王と姻戚関係を結んだフランク族クロヴィスがフランク王国を設立(481)したり、そのクロヴィスがカトリックに改宗(497)して、ゲルマン族のアレイオス派からカトリックへの宗旨変えが進み、結果としてアレイオス派が消滅する等の混迷を極めた時期である。
ボエティウスは教父ではなかったのに、アレイオス派であったテオドリック王に殺されたため中世には教父扱いされたそうだが、異端とされたアレイオス派に対するカトリックの憎しみというのは相当なものだということが解る。また同時にボエティウスはアウグスティヌスを継ぐ者でもあり、思考がギリシア教父の時代から次第に変質していく様子がわかる。すなわちアリストテレスの論理から離れていくのだ。その端的な例がこの三位一体論に現れている。三位を正当化するために三位は可算では無い故に三位が一体であるという論を持ち出すのである。一は一性であり、二は二性であるが故に一と二そして三は数えるものではないという論である。これは論理の上に立ってキリストの教えを理解するのではなく、三位一体がありきでそのためには論理は退くべきであるとも云うべきものであって、ギリシア人教父の深い考察と論理とローマ的な融和の内に打立てた三位一体の考えを根底から否定するものとなるのではないか。
■ 書簡集よりカール大帝の書簡(2022.12.2)
カール大帝が、手元に届く各地の修道院などからの手紙が、あまりに不味いのを見て、改めて、各地の修道院とそこに付属している教育機関に対し、教育のあり方について諭す書簡である。
カール大帝の人となりがよく窺われる書簡であって、例えば、良き行いをするのは重要で修道院においては、良き行いが成されている、とその存在意義を認めたのちに、ただし、行いの前に知ることがある、との一文を示し、一般教育の大事さを示すと云う、王者の懐の深さを表すと共に、論理的な在り方が優先することを確かに示している。彼の考え方がどこから生まれたものかは、更に調べる必要のあることは明らかであるものの、このような人物がヨーロッパを支配する人として存在したことが、後々ヨーロッパにどれほどの影響を与えたかは、容易に想像できるのである。行いは良きものである必要があるが、知ることはそれ以前に良し悪しを超越していることが、大帝の言葉として民衆に与えられたと云う事実は、誠に大きなでき事であろう。カール大帝の治世が、カロリング・ルネサンスの始まりである、とするのは大いに納得できる。書簡の締めくくりが、大帝の揺るぎない権威を示す文章であると云うのも感銘深い。
■ ■ ■