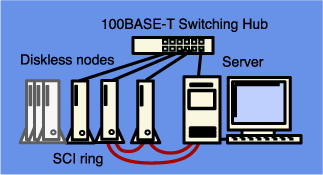やっと外部の金が使えることになったので、改めてノード間のデータ転送について考えてみることにした。まず、1000BASE-Tの話しだが、32bitのPCIでも使えるようだな。ただ、IntelのNICボードにも、Boot Agentは含まれていないというので、ノードのリモートブーツはできないようだな。これが\43,900だな。3COMのはもっと高いようだ。1Gといっても3分の1のスループットが出れば上々だろうから、1byte=10bitとして30MBぐらいだろう。
で、例のノード間のデータ転送のためのドルフィンだが、問題は結構な値段だ。ボードが@\177,000でケーブルが\42,000/1mだな。1次元トーラスを始めるために最低でもこれが2組必要だ。カタログデータでは170MBのスループットが出ると言うんだが。
さて、速度的にはイルカが5~6倍は早いだろう。100baseで今、各ノードが一斉に送信してもサーバでは順番に、ということでデータサイズがうんと大きい場合には10秒くらいの時間がかかる。1000BASE-Tで10倍早くなったとして1秒くらいか。だが許容範囲だな。計算する気層の数が増えても、ネットワークをうまく分割してサブサーバをおけば、そう時間は長くならないだろう。L2FTVを実行するシステムである限り、つまり、ネットワークのトポロジーを計算のパターンに合わせれば、問題は緩和できそうだ。
イルカを使えば、転送時間の問題は無視できるようになるな。ただ、値段の他にカーネルにパッチを当てなくちゃ、いけない所が気になるな。つまり、イルカは専用のメモリを占有する必要があるのだ。ユーザレベルからはシェアードメモリ型の並列計算システムになるわけだな。トポロジーは単なるリングから始まって二次元トーラスにするような、凝ったことができるようだ。だが、ボードの値段はどんどん高くなるな。
どっちが良かろう。別の問題として、1000BASE-Tの場合だと、スイッチングハブの値段が300,000位するので、買うとこれが設備になってしまう。受託の予算では設備分を用意していなかったので、実際には今回は100BASE-Tのハブを消耗品で買って、トポロジーのテストをするしかない。イルカならボードとケーブルなので消耗品扱いで全部買える。
こういうハードウェアだ。ノードはEtherを通じてリモートブーツする。データ転送を高速化するために専用のネットワーク(SCI)が組み込まれている。どちらが簡単か、という話しなら1000BASE-Tの方だな。ステップを踏んで考えてみると、各ノードにNICを入れてもブーツの時には100BASEのBootAgentが立ち上がって、TFTPを通じてカーネルをダウンロードし、システムが立ち上がる。で、ここで、1000BASE-Tの別のNICを使ってrootはNFSマウントできるだろうか。???だな。たしかNFSマウントするzImageは共通だったから、1000BASE-Tが活躍するのはMPIでノードを1000BASE-Tの名前で指定した時からだろう。ここらあたりは2枚差しで苦労したことを思いださにゃいけない。イルカではこれがどうなるかって言うと、カーネルにパッチをあてるからzImageから作らなきゃいけない。後は、全く別のI/Oだから、そんなに問題はないように見えるな、一見では。
どうも直ぐには答えが出ない。両方やってみるのが一番か。そうだな、ノードにNICを2枚差したらどうなるかは100BASEのカードでも試験できるしな。
ところで、ノードのCPUを取り替えるため、1GのPen-IIIを取りあえず2個、購入した。リテール品を入れたのだがヒートシンクが大きい。今のMBにはCPUソケットの周りのコンデンサが邪魔になって、ヒートシンクが付かないのだ。しょうがないので、以前に使っていたクーラを取り付けた。心配だったのでBIOSの温度データを30分ばかり見ていたが、ほとんど温度上昇がなかったので、そのまま使えるだろう。CPU負荷がかかったら温度も上がるんだろうが、その時はその時ということで。